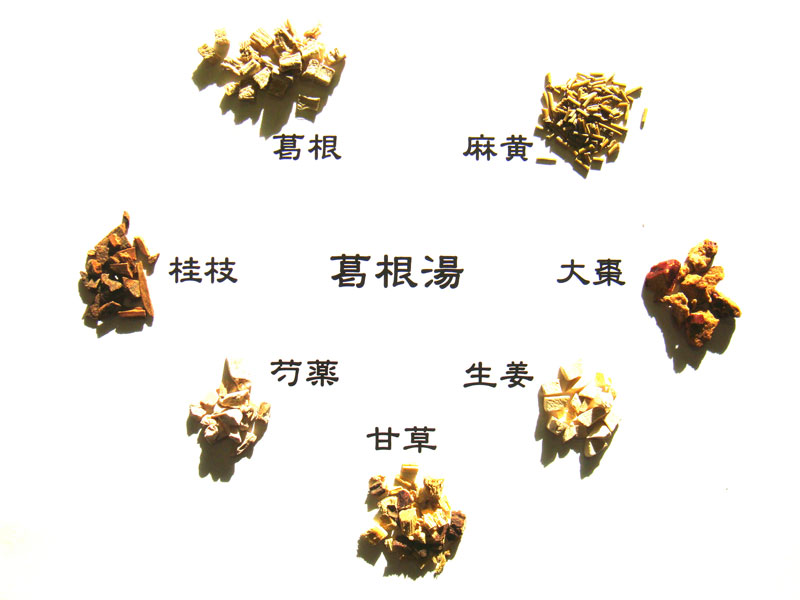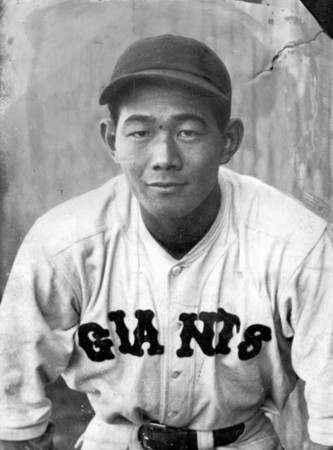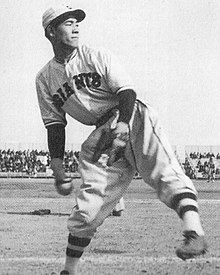浜辺に打ち寄せる波。
灼熱の太陽に背伸びでもするかのような椰子の木。

ハイビスカスの咲き乱れる木陰では、茶褐色の肌をした娘たちがゆったりとフラを舞う。

そう、ここは常夏の楽園「HAWAII」。
って、「長良川母情」の取材先が「ワイキキビーチ」であろうはずはない。
あまりの暑さで朦朧とし目も霞んだか?
両目を指先で押して見る。
だがどこからどう見ても目の前に立ちはだかる光景は、日本各地の山間で見かける長閑な農家だ。
「ああっ!」。
「あれ全部私がコツコツと描いたの!」。
納屋の真っ黒な壁面が、日本の原風景の中に突如として現れたワイキキビーチに占拠されている。
「中の庭も南国ムードたっぷりよ」。
ほんの2時間ばかり前に知り合ったばかりの律っちゃんは、そう言いながらぼくを中庭に招き入れた。
なるほど庭の中心に横たわる池の周りで、南国ムード満点に色とりどりの小物たちが真夏の太陽を弾き返す。
「ちょうどお昼やし、お弁当ついでに頼んどいたから一緒に食べよ!」。
レディーのお誘いとあらば、断るのも無粋。
早速ご相伴に与る事に。
ぼくの一番新しいガールフレンド「律っちゃん」は、本名清水律子さん(68)。
長良川鉄道の郡上大和駅を東へ向かった、156号線手前の喫茶店「横道」のママさんだ。
律っちゃんは、昭和36年に製材業の二代目を継ぐ故真志さんと結婚。
一男一女に恵まれた。
「青年団のフォークダンスで出逢って、私に一目惚れやて」。

しかし家業の製材業は、輸入材の普及と共に衰退の憂き目に。
「子どもが小学校へ上がったころ、いつか自分で店開こうと調理師免許取ってね。それで昭和46年に開店したんやて。でもそれが大変やったんやて。親戚中から『水商売はあかん』って、挙句に家族会議で大揉め」。
律っちゃんは一人大笑い。
それから10年の歳月が流れたある日。
「小さな竹の橋」というハワイアンの名曲に心奪われることに。
「『ああ、私も踊ってみたい!』って、魂が掴み取られるような感じ。でもまだ子育てもあるし、その想いは心の奥にしまい込んだんやて」。
目まぐるしい日常の中、すっかりフラへの想いも消え入りそうになった頃、夫が癌を発病。
「治療が始まって、残りの人生二人で一杯思い出作ろうって、旅に出るようになったの」。
そんな日々が3年も続き、癌の進行も止まったかに見えた。
「主人もすっごい元気になって来て。『こん時やあ』って、フラの教室に通いたいって切り出したの」。

しかし半年後に容態は急変。
「結局156日間も病室に泊り込むことに。でも主人とよく笑ったわ。『三食据え膳で二人っきり。まるでリゾート気分やね』って」。
今年七回忌が無事営まれた。
「でもフラのお友達が一杯だから、寂しくなんてないし、お店は午前中だけ開けてお客さんに遊んでもらってるの。呆け防止にね」。
フラガールの母、律っちゃんは真夏の太陽を恋しそうに見つめた。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。