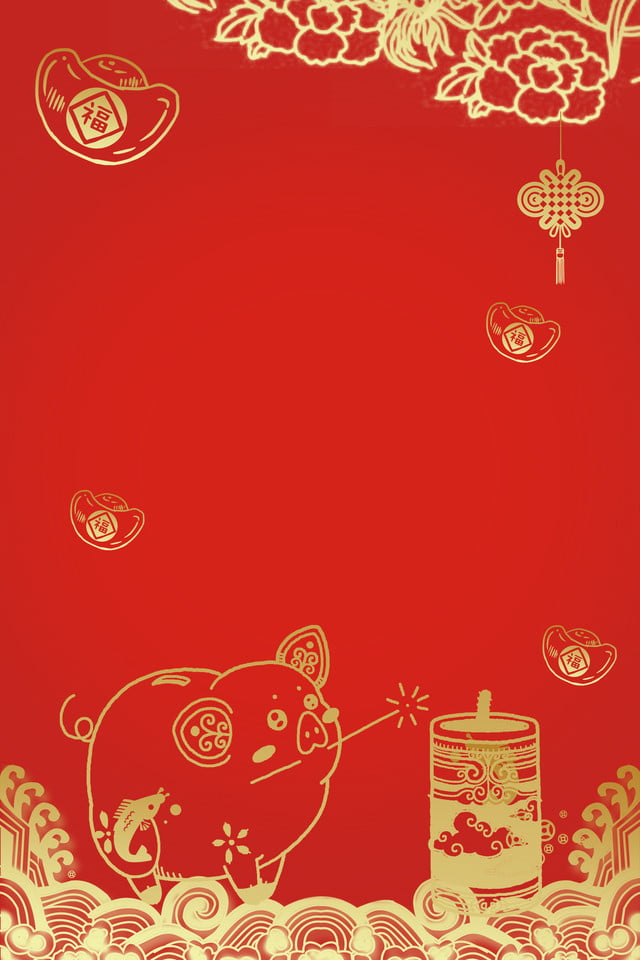今日の「天職人」は、愛知県西枇杷島町の「粕漬職人」。
祖母の倹しい食卓は いつもの煮物とお漬物 パリポリパリポリ音立てて お茶漬けスズッと一啜り 祖母の齢に近付く度に 倹しいお膳がご馳走に パリポリパリポリ音立てりゃ 旬を彩る香の華(はな)咲く
愛知県西枇杷島町で明治2(1869)年創業の、尾張屋五代目の太田隆夫さんを訪ねた。

「毎年母の日が来るのが、一番嫌でな。何で俺だけ白いカーネーションなんやって」。隆生さんは遠い日を振り返った。

昭和19(1944)年、三歳の隆夫さんを遺し、父清六は中国で戦死。まるで夫の後を追うように、隆夫さんの小学校入学前、母昌子も病に冒され還らぬ人に。「父の記憶なんてありませんわ。唯一母との写真がたったの一枚」。出生からわずか六年で不幸の渦中に。隆生さんの祖父母は、誕生前に既に他界。よって明治気質の曾祖母に育てられた。
大学を出ると先輩職人に付き、修業を開始。「私、酒呑めへんのですわ。でも酒粕の匂いがプンプンする蔵の中に、一日おっても全然酔わんで不思議なもんや」。

昭和43(1968)年、遠縁に当たる歯科医の娘、富子さんが嫁入り。「身寄りのない私を案じ、お見合い写真がようけ持ち込まれとったわ。そんな頃、歯の治療してもらっとる時に、コレの親父である先生に相談したら『そんなもんより、家の娘の方がええに決まっとる』と脅されて」。しかし本心は、富子さんの顔見たさで、わざわざ東区までせっせと歯の治療に出掛けていたほど。
尾張に唯一、昔ながらの伝統製法が受け継がれる守口漬けは、真冬の塩漬けに始まり、一番粕から三番粕へと。酒粕、味醂粕、塩、砂糖で漬け込まれ、徐々に塩分を抜き去り、酒粕や味醂粕の旨味を封じ込める。足掛け三年の歳月が惜しみなく注ぎ込まれ、芳醇な香りを漂わせ、尾張屋と銘打たれた化粧樽に、真心を添え詰め込まれる。

長男光則さんは五年前(平成十五年九月三十日時点の新聞掲載日より五年前の平成十年)、東京の就職先から妻を伴い後継修業のため帰郷。全てが順風満帆に見えた二年後の九月。東海豪雨が一帯を襲った。工場は全滅。「味噌糞一緒や。町の中を樽が流れ出し、冷蔵庫はプカプカ浮いとるし」。何もかもが失われ、思わず廃業の二文字が脳裏を過った。しかしその二日後、初孫が産声を!「もう一度、家族皆で力を合わせて頑張ろう」。初々しい父親となつたばかりの光則さんの言葉には、六代目としての不屈の決意が宿っていた。そして末の弟も加わり、尾張屋復興に向け後始末に奔走した。

親の温もりも知らず、面影だけを暖簾に重ね、店を守り抜いた粕漬職人は、水害の災いさえも、新たな命の誕生で福と転じ、家族の絆をより強固に紙縒(こよ)り上げた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。