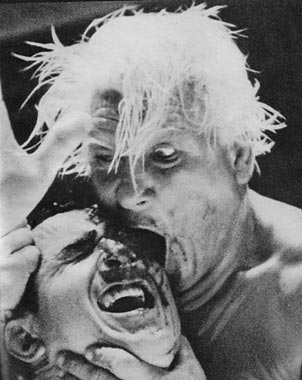※一部キャンセルが生じたものの、残席僅かとなりました!ご参加をご検討中の方は、どうぞお早目のご予約をお願いいたします!
「オカダミノルほろ酔いLive2026~withケージ東」開催のご案内
●日 時:2026年4月12日(日) 14:00開場、14:30頃開演、 16:00終演予定
●会 場:「奥柳演芸場」 https://www.facebook.com/ao.liubesu/ 岐阜市柳ケ瀬通6-12 080-4535-9320(担当/清水一美)
●出 演:オカダミノル ケージ東(Pf.)
●参加費:お一人様Live Charge 4,000円
●定 員:50名(全席自由席)
●申込み:メールで、horoyoilive@yahoo.co.jp「オカダミノルほろ酔いLive2026~withケージ東」係まで。
●締 切: *先着順、定員となり次第締め切り
●問合せ:horoyoilive@yahoo.co.jp
●主 催:オカダミノルほろ酔いLive実行委員会
※二次会のご案内
ライブ終了後、17:00頃~会場周辺か或いは、名鉄岐阜駅周辺の居酒屋で、二次会を開催いたします。(参加費は、お一人様 約3.000円程度を予定)二次会への参加希望の方は、「二次会参加」とライブの申し込み時にお書き添え願います。


※遅まきながら、ぼくもフェイスブックとやらを始めました!まだまだ充実しておりませんが、ぜひ一度お越しください!Facebook
今日の「昭和Nostalgia」はコチラ!

小学校も高学年になった頃、こんな学級委員のバッヂを胸に付けたくって、それ一心で風紀委員に名乗り出たことがありました。

風紀委員が何をするのかなんて、これっぽっちも判らず、ただただバッヂを胸に付けたい一心であったと思います。

お母ちゃんが胸元にバッヂを飾るため、タバコくらいの大きさのフエルト生地に、バッヂを取り付け、フエルト生地の裏側に安全ピンを付け、服の胸元に取り付けてくれたものでした。

なんとなくそれだけで、誇らしい気分になったから不思議な気分でした。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4eae7dff.11d28e3b.4eae7e00.7b731596/?me_id=1195745&item_id=10000016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmasuyone%2Fcabinet%2Fgoods%2F08472711%2F750x750.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)