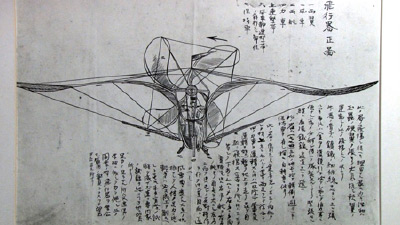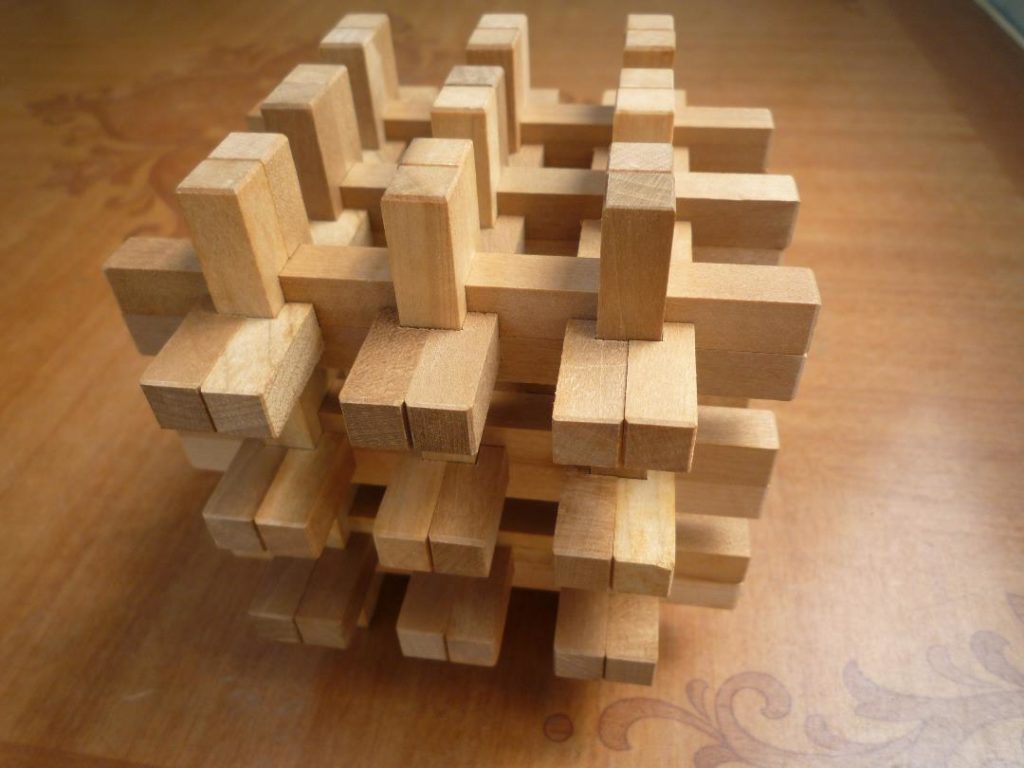今日の「天職人」は、岐阜市神田町の「田楽職人」。(平成十七年十月十一日毎日新聞掲載)
季節を愛でる旬ならば 春夏秋冬それぞれに 味わい深い恵みあり 菜めし田楽里の秋 濡れ縁越に虫たちも わずかな秋を惜しみ鳴く 遠くに響く笛太鼓 豊年祝う村祭り
岐阜市神田町、木の芽でんがく処「むらせ」の三代目主人、村瀬善紀さんを訪ねた。


「家の田楽食べて、後十五年は生きるんやて」。 義紀さんはそう宣言した。
「祖母が明治三十五(1902)年に、岐阜公園の中の茶店で、田楽を焼き始めたんやて」。
善紀さんは昭和十(1935)年に、煎餅職人の父と、祖母と田楽屋を切り盛りする母との間に、長男として誕生。
地元高校から東京の大学へ。寮生活が始まった。母は息子の食生活を案じ、田楽味噌を送った。「寮で奴が出たから、味噌付けたんやて。そしたら皆が俺もって、あっと言う間に売り切れ」。
大学を出ると名古屋で就職。社会人チームで、サッカーボールを追いかけた。堅物で不器用なスポーツマン。そんな善紀さんに転機が訪れた。
毎日仕事で顔をあわせる、娘のことがどうにも脳裏から離れない。堅物男が勇気を出して放った、純な想いのシュートは、娘心のゴールネットを揺らした。
昭和三十七(1962)年、名古屋出身の英子さんを嫁に迎え、二男一女が誕生。
やがて昭和も五十(1975)年代へ。父が病を発病し、わずか一年で他界。焼き手を失った煎餅屋は、他所から仕入れ妻が子育ての傍ら店番を担当。
昭和五十二(1977)年、善紀さんは四十二歳で会社を辞し家業を継ぐことに。
「でも主人は、直ぐに調停員の仕事についてしまって」。
煎餅屋を建替え、田楽処の二店舗目を開き、結局英子さんが店を切り盛り。
「私はもっぱら、妻の田楽で一杯やりながら接客担当。それと代々続く、家の田楽の味の監視人やて」。
代々地元の豆腐を仕入れ、三分の一丁を六つに切って串を打ち、まずは素焼き。
八丁味噌に秘伝の味付けを施し、四時間かけて細火で煮込んだ味噌を塗り、再び竈(くど)で炙る。

「家の田楽がやっぱり一番旨い」。義紀さんは、各地の田楽を食べ歩いた。
「『味噌分けてもらえんか?』って言うお客さんも見えますが、『味噌だけ売るべからず』を信条に、お断りしとんやて。やっぱりこの土地の恵みは、ここで食べてもらわんと」。
「さあどうぞ」。英子さんが熱々の豆腐田楽を差し出した。

串から焦げた味噌の香が立ち込め、鼻をくすぐる。
口中に田の恵み、豆腐と味噌の、共に大豆の絶妙な魔法が広がる。
媚びるような甘さなどいらぬ。ただ辛口の、冷酒一献あればいい。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。