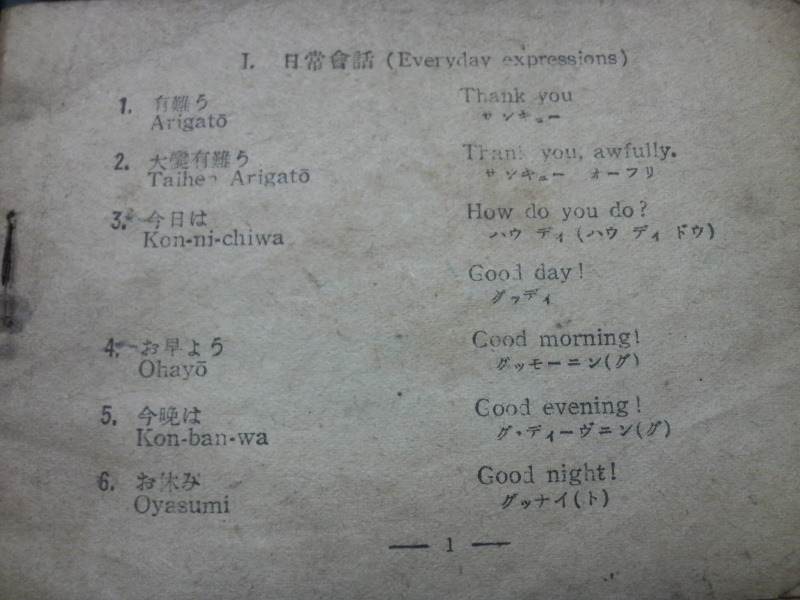今日の「天職人」は、岐阜市徹明通の「甘納豆職人」。(平成十九年九月十一日毎日新聞掲載)
稲刈り終えた畦道を 真っ赤に染める彼岸花 「彼岸にゃ顔を見せろよ」と 母の墓参の道標 年に一度の不義理侘び 母の好物甘納豆 木箱で手向け香焚けば 傍(はた)で娘が摘み食い
岐阜市徹明通、甘納豆の岡女堂。三代目甘納豆職人の青山邦裕さんを訪ねた。

杉の木箱に納められた、色とりどりに艶を放つ甘納豆。
お正月が待遠しかった遠い日。
何とも馨(かぐわ)しく思えてならなかったお節料理に似ている。

「大納言に斗六(とうろく/大福)、それに金時、青エンドウ。同じ豆でも金時は直ぐに水に浸かるんやけど、大納言はなかなか浸かりません。だから冬場はぬるま湯に浸して」。邦裕さんが人懐っこい笑顔を向けた。
邦裕さんは昭和30(1955)年、三人兄妹の長男として誕生。
一浪の末、大学へと進学。
「家業を継ぐつもりもなく、好きなことがしたくって。だって小さい頃から、家の中では嫁姑の喧嘩ばっかりで。そりやあ四六時中、互いに顔を突き合わせとるんやで」。
ところが程なく父が入院。
大学を一年で中退し、急ぎ帰省し家業を継いだ。
「まぁ、もともと物作りは嫌いじゃなかったんやて。そう言えば、中学の時に祖父から『丁稚に行くか高校行くか』って、真顔で問い詰められたわ」。邦裕さんは懐かしそうに目を細めた。
それからは「技は見て盗め」の、言わずと知れた職人道。
「とは言え幼心に祖父や父、それに職人の後姿を見て育ちましたから、抵抗なんかありません。小さい頃はよく、おやつ代わりに工場で甘納豆摘んだり、泥饅頭捏ねて和菓子作りを真似たもんやて」。蛙の子は蛙。ものの数年で立派な甘納豆職人へ。

昭和55(1980)年、関市出身のまち子さんと結ばれ一男一女を授かった。
「取引先の事務員でして。友人たちと一緒にスキーに誘って。それからは毎週飛騨までスキーへ。それが二人のデートやて」。照れ臭そうに店の奥を盗み見た。
甘納豆作りは、北海道産の厳選された豆を水に浸すことに始まる。
翌日豆を煮て灰汁(あく)を出し渋を抜き取る。
次に編み籠に豆を移し、重曹を入れ再び煮汁が吹き零れるまで煮上げる。
「重曹を入れると皮が早く柔らかくなるんやて」。
次に柔らかく煮上がった豆を、暖めた砂糖蜜の中に一晩浸け込む。
「豆の中に砂糖が浸み込んで、皮の外に豆の含んでいた水分が出て、砂糖蜜がしゃびしゃびになるんやて。それで砂糖蜜を濃くしてもう一晩浸け込むんやわ」。
翌日、蜜浸けの釜のままとろ火で温度を上げ、豆の芯まで温まったところで再び甘みを高め、火を落とし三十分程置いてから編み籠を上げ蜜を切る。
そして仕上げに、切りだめと呼ぶ大きな盆に紙を敷き、その上に豆を広げて二十分程晒し、冷めたところで上からグラニュー糖を塗せば完了。
「時間だけはかかっとるけど、手間はそれほどかかっとらんのやて。ただボ~ッとしとるだけやし」。
保存料や添加物は一切無い。
だから日持ちも一週間ほど。
「昔は砂糖の量が多かったから、一ヵ月は日持ちしたんやけど、今は何もかも糖分控えめの時代やで」。
豆と砂糖と水だけを原料に、時間と手間と己の技を、職人は惜しみなく注ぎ込む。

硬質な一粒の豆は、至福の柔らかさを纏い、名代の甘納豆へと生まれ変わる。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。