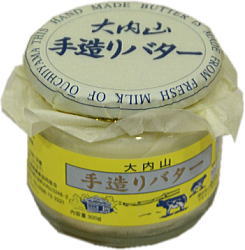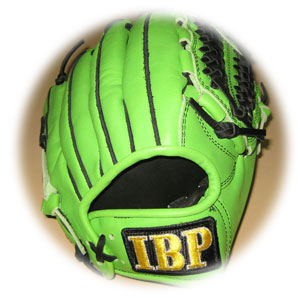今日の「天職人」は、岐阜市長住町の「ホルモン屋女将」。(平成十九年十二月二十五日毎日新聞掲載)
色付く街に賛美歌と 恋人たちのはしゃぎ声 あんな時代もあったなと ネクタイ緩めコップ酒 レバーにネギマ ホルモンと 上司の愚痴をアテにして 酒を煽って憂さ晴らし オヤジ二人のクリスマス
岐阜市長住町のホルモン水谷本店。二代目女将の水谷信子さんを訪ねた。

「おお~い、酒二杯に串三本やで勘定おいとくわ」。
夜も更けた光景かと思いきや、まだ昼下がりの午後二時半だ。
名鉄岐阜駅を西に入ったビルの谷間。
歩道に突き出した煙突からは、炭火に爆ぜる美味そうな肉汁の香りが漂う。
歩道をゆけば、ついつい袖を引かれそうになるのが人情。
それが証拠にこんな真昼間から、店内はもう鈴鳴り状態。
店から溢れ出した客用に、ビールケースに板を載せた簡易テーブルが組み立てられ、客も手慣れた様子で丸椅子を運び出し、歩道脇に陣取ってコップ酒を煽る。
「家の名物は何てったって、厚切りレバーやて」。信子さんが、串盛りを差し出した。

「まあお茶菓子代りに食べてみたって」。
確かに串に刺さったレバーの厚みは、2㌢近くもある。
まるで学校給食に添えられていた、三角形のチーズ大の大きさで、おまけに惜しげもなく一串に二切れという大胆さ。
これで一本百円とは、鈴鳴り人気にも合点がいく。
信子さんは昭和18(1943)年、一文菓子屋を営む後藤家に誕生。
中学を出ると化粧品屋に勤務し、看板娘として販売を担当した。
ちょうど娘盛りの20歳を迎える頃の事だ。
「練炭屋に夫を紹介されたんやて」。信子さんは心なしか照れ臭げだ。
「旅館をやってた叔母が『下見してきたるわ』って、この店にこっそりやって来て夫の品定めやて。それで『三郎さんなら間違いない』って、太鼓判押すもんやで」。
昭和38(1963)年、水谷家の二代目三郎さんに嫁ぎ、二女を授かった。
「当時も店はてんてこ舞い。だから娘二人は住み込みのオバサンに任せっぱなし」。
高度経済成長期を支えた男たちは、ホルモン屋でまずは景気を付け、ネオン瞬く柳ヶ瀬へと繰り出していった。
「よう明治気質の義父から教わったもんやて。『飲み過ぎた人に売っちゃいかん』って。だから今でもそれは肝に銘じとるんやわ」。

平成12(2000)年、夫が他界。
「もう二代限りで終わりにしようかって思っとったんやて。そしたら娘婿が、『俺が会社辞めて継ぐ』って涙浮かべて言ってくれたんやわ」。
信子さんは言葉を詰まらせながら、誇らしそうに焼き場の娘婿を見つめた。
「わしなんか忘れたくらい昔から、ほとんど毎日通っとるって。値上がりせんし、隠居の身には助かるんやて。だから勘定も自己申告みたいなもんやって」。
帰り際に常連客の老人が笑い飛ばした。

思い思いの客がそれぞれの人生を引っ提げ、小さな丸椅子に腰かけ赤ら顔で串を頬張る。
ここでは会社の看板や、身分の上下など一切通用しない。
だからこの店が大人たちの止まり木であり、楽園であり続けるのだ。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。