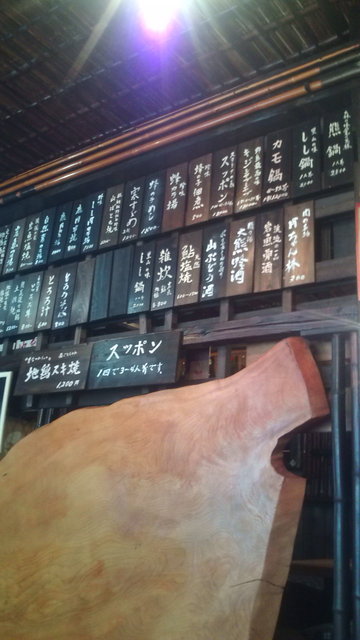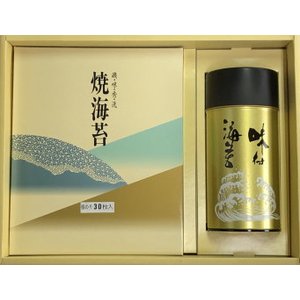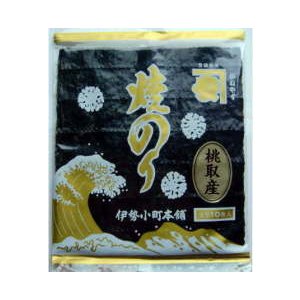今日の「天職人」は、岐阜市八ツ寺町の「高等ライス職人」。(平成20年2月26日毎日新聞掲載)
明治生まれの爺ちゃんは 着物姿にパナマ帽 雨も降らぬに蝙蝠(こうもり)を コツコツ鳴らし町を行く
「馳走したろ」と洋食屋 おい」と爺ちゃん手を上げりゃ オヤジも「ヘイッ」とうなづいて 高等ライスお目通り
岐阜市八ツ寺町の三河亭、四代目主人の中島稔さんを訪ねた。

何とも不思議な商品名の「高等ライス」。
米の等級を示すものなのではない。
無論、高等学校の給食に端を発したものでもない。
列記とした明治生まれの由緒ある商品だ。
白い丼に炊き立てご飯。
その上に自慢のカレーが盛られ、最上段に目玉焼きを冠した不思議な逸品。

「家は明治27(1894)年に、愛知県豊橋市出身の初代が創業したんやけど、当事のカレーと言えばちょっとした高級品。だけど『高級ライス』じゃ何や可笑しいし、挙句に思い付いたのが『高等ライス』だったんやて」。稔さんは、悪戯っ子のように笑った。
稔さんは同市でスポーツ用品店を営む森田家の三男坊として、昭和26(1951)年に誕生。
高校を卒業すると大阪へ出て、スポーツ用品の卸問屋に勤務した。
「一人暮らしで自炊の毎日やったわ」。
26歳の年に名古屋支店に転勤。
しかしその2年後、母が病に倒れ家業を手伝うため会社を辞した。
「ある時、ここの三河亭と付き合いのある客が、スキー用品を探しに来とって、そんなご縁で家内と見合いする話しになったんやて」。
見合いが終わると婿入りを前提に、三河亭で見習いを始め調理師免許を取得した。
昭和55(1980)年に中島家に婿入りし、一人娘の京子さんと結婚。
一男一女を授かった。
「30歳までに結婚せなかんと思って、切羽つまっとったで」。稔さんは照れ臭げだ。
「三代目は妻の父なんやけど、妻が7歳の時に若くして亡くなってまっとったんやわ。だで私は二代目の祖父に教え込まれたんやて」。
店の客は誰もが、新参者の稔さんより、遥かに三河亭の味に肥えた手練(てだ)ればかり。

「何しろあっち向いてもこっち向いても、先輩のお客さんばっかなんやって。お客さんの最高齢は90歳で、郡上から年に2~3回見えるんやけど、そのお歳でタンシチューを一度に二人前ペロッと召し上がるんやで」。
代々主人が自らの舌に叩き込んだ歴代の味。
少しでも異なれば、通い詰めた客にたちまち見破られる。
名代の逸品「高等ライス」は、小麦粉をオーブンで炒って何ヵ月も寝かし保存することに始まる。
炒って熟成させた小麦粉を取り出し、スープを加え肉や野菜と共に一時間ほど煮上げる。
そうして手間隙かけて仕込み上げた秘伝のカレーを丼飯の上に盛り付け、最上段に目玉焼きを載せれば114年前と寸分違わぬ高等ライスが完成する。

「ご年配の人にも贔屓にしていただき、お出掛けの時なんか、わざわざ寄ってくださり、家のカツサンド持ってかれるほどやて。まったくありがたい話しやわ」。
「育ての親は客だ」と言い切り、家伝の味を護り抜く。
天晴れ高等ライス職人。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。