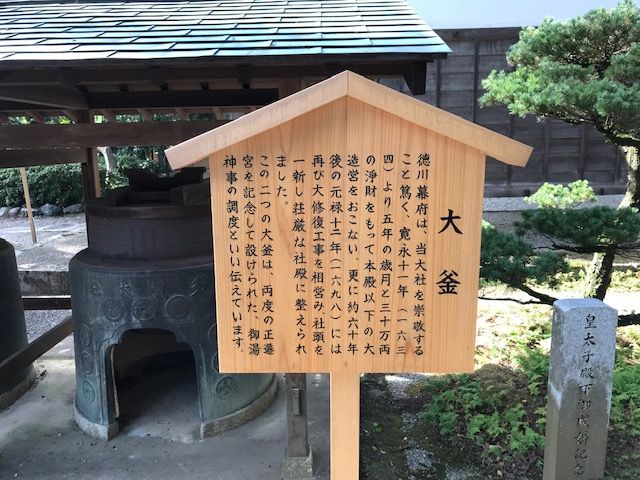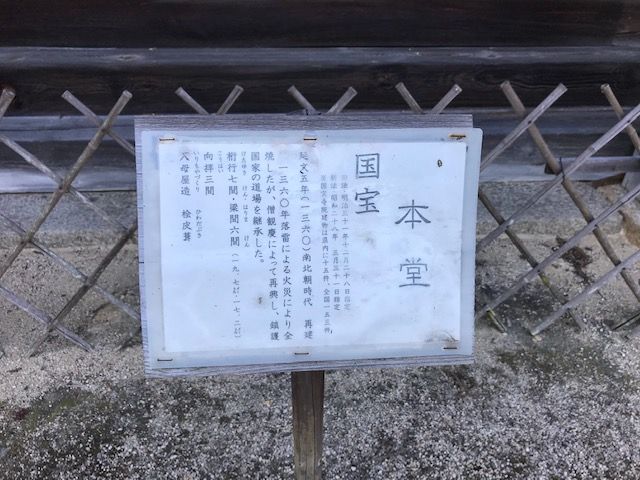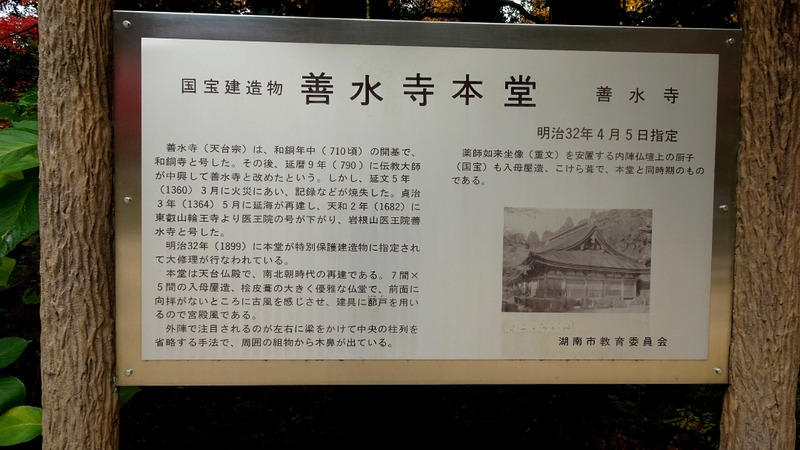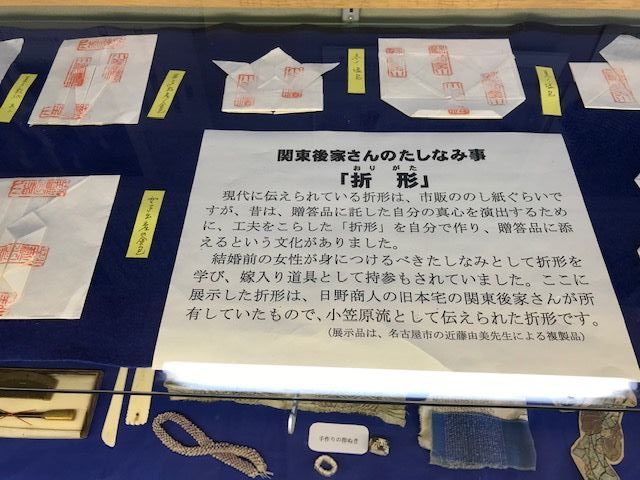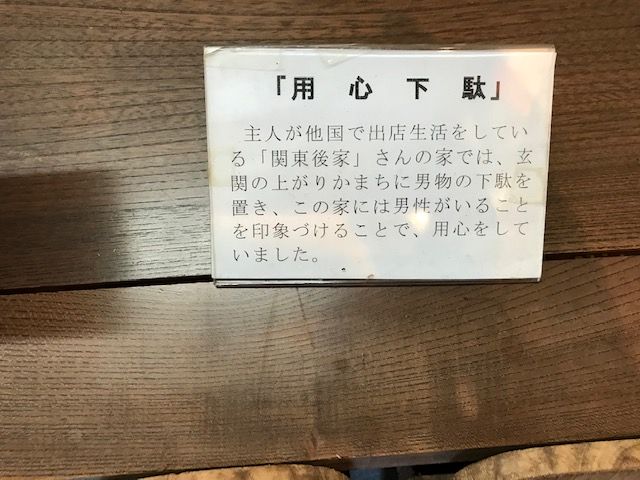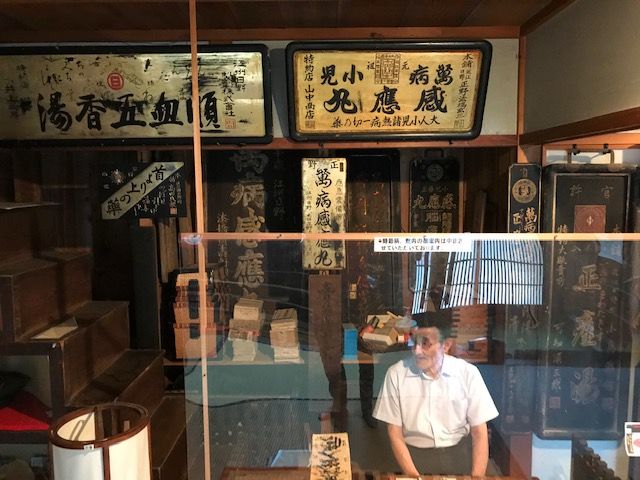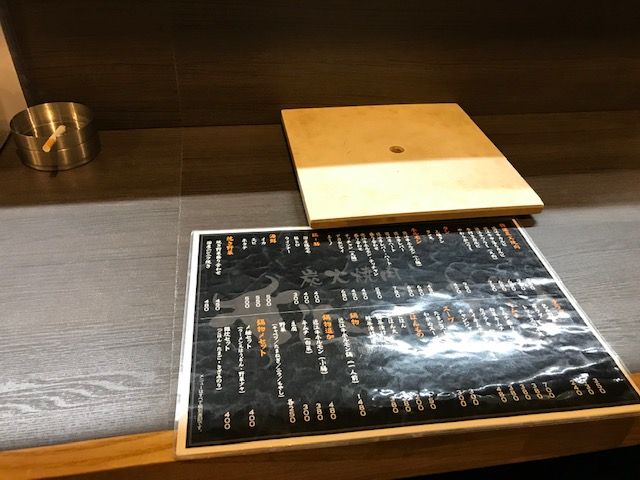今日の「天職人」は、愛知県吉良町の「浜採り」。(平成20年5月20日毎日新聞掲載)
吉良の白浜夜も白(しら)みゃ 浜採りたちが塩田へ 平(ひら)で砂撒き腰を振る 満ち潮までの一仕事 潮が引いたら天日干し 満鍬(まんぐわ)曳いて砂返す 夏の初めの昼下がり 塩焼き小屋に煙立つ
愛知県吉良町で先祖代々浜採りを務める、渡辺友行さんを訪ねた。

「浜採りにゃ盆も正月もあれせん。天気のいい日は、朝から夜中まで働き詰めだわ」。友行さんは麦藁帽の庇を押し上げ、潮焼けた赤ら顔で笑った。
「この辺一帯は、あの赤穂浪士で敵役に祭り上げられてまった吉良公が、干拓地として築いた新田だで、土壌に塩分が含まれとって作物が出来んかっただ」。
波穏やかな三河湾の内海。
その特性を活かし、入浜式塩田へ。
いつしか吉良の饗庭塩(あいばしお)と呼ばれ矢作川を舟で遡上し、豊田市足助町で中馬に積み替え、長野県塩尻市まで運ばれた。

饗庭塩は塩の尻の終着点を目指し、「塩の道」を旅した。
友行さんは大正15(1926)年に長男として誕生。
尋常高等小学校を出ると家業に従事した。
「白浜地区でも一番広い2反7畝(約27㌃)の塩田があっただ」。
300年の歴史を誇る吉良の饗庭塩作りは、夜明け前から始められる。
まず平と呼ぶ木製の平らなショベルに砂を載せ、浜採りたちが腰を使い塩田に砂を撒く。

やがて陽が昇り潮が満ち、砂を濡らす。
すると幅2間(約3.6㍍)もある巨大な満鍬(まんぐわ)を曳き、手返しで砂を乾燥。
砂が乾けば、寄せ振りで砂を集め沼井(ぬまい)へ。
その上から海水を掛け流し、砂に纏わり付いた塩を流し落す。

沼井は約1㍍四方。
木製の風呂桶のようだ。
底部には簾が張られ砂を堰き止める。
さらにその最下層には空洞があり、濃度を増した海水が流れ込み、取り出し孔を伝って壷桶へと流れ出す。
「潅水(かんすい)を柄杓で汲み取って、桶を肩にいなって塩焼き小屋へ。最初に砂で濾過して、今度は家畜の骨を焼いて作った骨炭で濾過するだ。次に釜に入れて石炭で2時間ほど煮詰めた後、ドサへ苦汁(にがり)を含んだままの塩を掬って入れとくだ。やがて苦汁が簾から流れ出せば饗庭塩の完成だわ」。
昭和20(1945)年、戦火が激しさを増す中、三河大地震が大地を引き裂いた。
「もう塩焼き小屋は壊滅だわ。それからは潅水取って、それを売って生計に充てたとっただ」。浜採りは沖を見つめた。
昭和24(1949)年、ふじゑさんを妻に迎え、一男一女を授かった。
だが昭和28(1953)年、13号台風が三河湾を直撃した。
今度は塩田そのものが壊滅。
友行さんはその後、農業に酪農、温室園芸などで家族を支えた。
「農業では食うてけんで、昭和47(1972)年に喫茶店を始めただ。店の名前の由来か?そりゃあ女房の名前『フジ』だわさ」。
昭和も終わりが近付くと、塩作りの再現話しが舞い込んだ。
「私らの年代が最後の浜採りだで」。
今週土曜日から9月までの第4土曜日に、吉良町の復元塩田で一般参加の饗庭塩作りが始まる。
「これからは月1の浜採り復活だで、生きとるうちに若いもんらに饗庭塩作り伝えとかんと」。
浜採りは沖行く海鳥を見つめながら、ぼそりとつぶやいた。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。