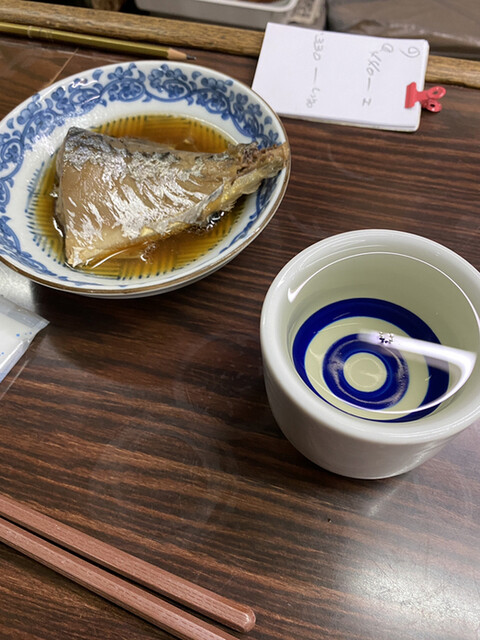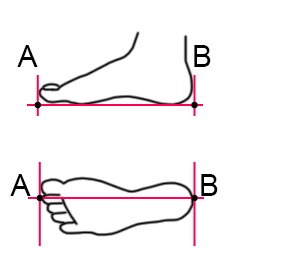今日の「天職人」は、三重県四日市市の「大入道せんべい職人」。(平成23年7月30日毎日新聞掲載)
狸囃子か腹太鼓 里の童も化かされて 酒と肴の供物下げ 狸の穴で額ずいた それを見ていた子狸が 里の菓子屋で子に化けて 大入道の焼印の 煎餅盗み腰抜かす
三重県四日市市で昭和8(1933)年創業の、四日市名物大入道せんべいの宝来軒。三代目煎餅職人の森秀明さんを訪ねた。

せんべいの袋の中に入った、厚紙を切り抜いた大入道。

裏面には、大入道の謂れ書き。
大入道は頭が青々と剃り上がり、太い眉に大きな眼。
団子っ鼻に真っ赤な舌が、顎の下へと垂れ下がる。
白黒縦縞模様の着物に赤い帯。
厚紙の一方を上へ押しやると、大入道の首がドロロンと伸びる、極めて簡単な、昔ながらの仕組みである。
しかしこの大入道。
どこからどうみても怖いと言うより、むしろ滑稽であり親しみさえ感じてしまう。
「昔、四日市の港には、蔵がようけありましてな、そこへ狸がやって来ては蔵荒しをしよって。地元の衆が困り果て、狸を驚かそと大入道を作ったんやさ。ところが狸もしたたかで、逆に大入道に化けられる始末。これはあかんと、大入道に細工して首がドロロンと長くなるようにしましたんさ。それでさすがの狸も驚いて、尻に火い付けて逃げ帰ったとか」。秀明さんが、その由来を語った。
「今も、文化2(1805)年に作られた、高さ5㍍、首の長さ1.6㍍、着物36反の超大型の大入道が、山車に乗って町を練り歩きますんさ」。

秀明さんは昭和39年に3人兄弟の長男として誕生。
昭和59年、製菓の専門学校を出ると、名古屋の洋菓子店に住み込み修業へ。
「6畳一間に4人住まい。朝4時半から夜中の11時まで。面接の時に親方は、そんなこと一言もゆうとらなんかったのに。とにかくよう殴られましたわ。親方はえらい任侠道に憧れとって。部屋へ呼ばれると極道映画のビデオ見せられ、『お前らなあ、任侠も菓子の道も同じや』って。せやでぼくがおった6年の内に、10人が夜逃げしてもうて」。
平成2年、5年の満期にお礼奉公の1年を勤め上げ、家業へ戻った。
「ちょうど祖父が他界しましてな。そしたら親方がどこぞかで、黒のベンツのレンタカー借りて来ましてな。『これ乗って里へ帰って来い!死んだ爺さんに、ええとこと、男気見せたらんかい』って。今思うとええ親方でしたわ」。
祖父が遺した大入道せんべいを、来る日も来る日も父と共に焼き続けた。
平成11年知人の紹介で、鈴鹿市から悦子さんを妻に迎え、やがて一男二女が誕生。
78年続く郷土の味、大入道せんべいは、今も祖父の代と変わらぬ配合と作り方が続く。
まず卵、砂糖、蜂蜜、バター、小麦粉、膨張剤を配合しミキサーで捏ねる。
次に生地を鉄板に敷き、その上から鉄板を被せて挟み、両面がこんがりするまで焼く。
焼き上がったところで、大入道の絵の焼き鏝で焼印を入れれば完成。

「簡単なようですが、季節によって寒暖も湿気もちごてきます。せやでその都度、配合も微妙に変えやんと」。
盆暮れの無沙汰を侘びる手土産は、今も変わらぬ大入道。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。