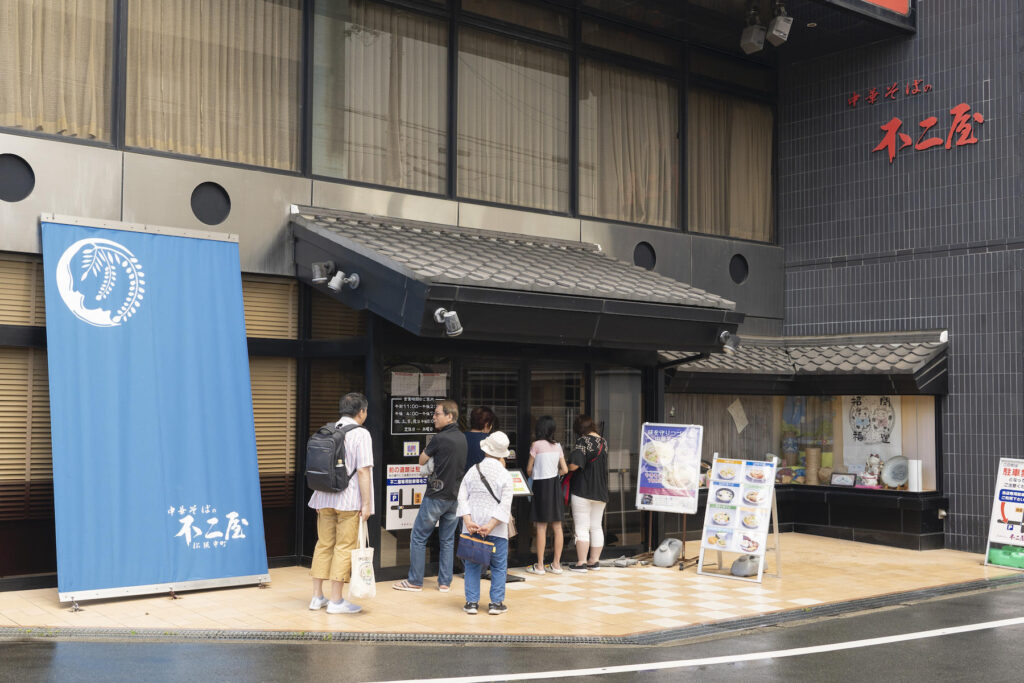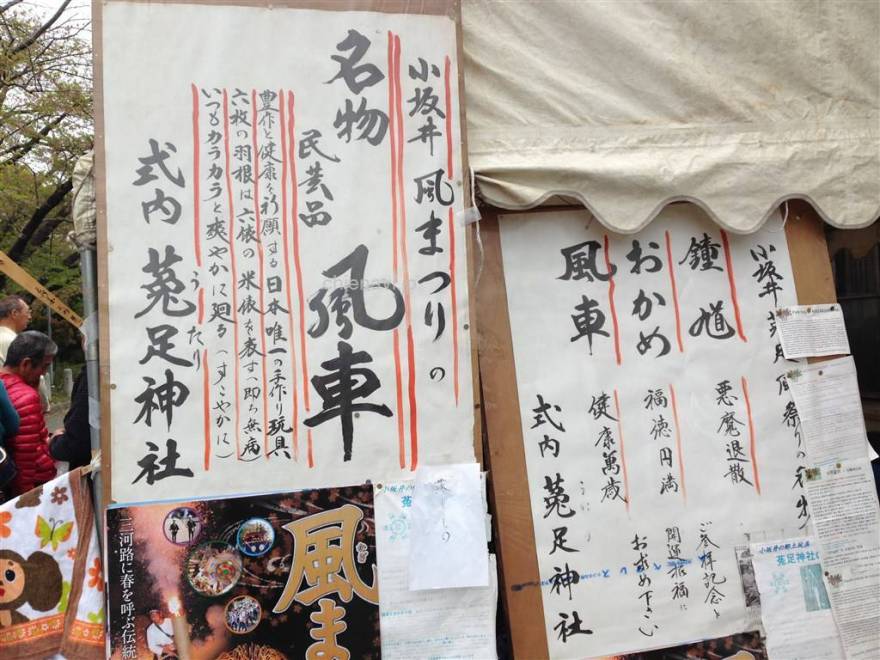今日の「天職人」は、愛知県東海市大田町の「手焼海老せんべい職人」。(平成22年2月24日毎日新聞掲載)
内職仕事手を止めて 母は欠伸を噛み殺し 音羽屋海老せんパリポリと ズズーッと啜る出涸らし茶 母の唯一贅沢は 知多のアカシャの海老せんべい 他所で見切りの品を買い 音羽屋だけは正札買い
愛知県東海市大田町で、大正初めに創業された音羽屋。知多の港でその日水揚げされたばかりの、新鮮なアカシャエビだけを使った、正真正銘の海老せんべいの老舗。女主と呼ぶにはおきゃんな、前田佐知子さんを訪ねた。

「四代目が私です」。佐知子さんだ。
佐知子さんは昭和49(1974)年、浅井家の次女として誕生。
音羽屋の仕事は、昔も今も変わらない。
早朝の魚市場での仕入れに始まり深夜まで。

「だから両親なんて、一度も運動会に来てくれたもことないし」。佐知子さんは表通りで遊ぶ、我が子を見詰めた。
「小っちゃい頃から『お前は死んだ兄ちゃんの変わりや』って言われ…。高校生の頃には、魚市場で父に仕入れの手伝いさせられとったもん」。
高校を出ると得意の英語を活かそうと、国際観光専門学校へ。
「でも姉も嫁ぐと、誰があの重いエビを運ぶんだろう。やっぱり就職は無理かって思ってました」。
専門学校を出ると、家業の手伝いの傍らケーキ屋や自動車会社でアルバイト。
「年頃だったし、ちょっとは他所の世界も見たくって」。
平成10年、年老いてゆく両親を見かね、家業に専従した。
「私は父が40歳の時の子だったからか、普段はものすごく優しくて。でも仕事になると超ど一刻。足の骨折れても添え木して、生地には絶対触らせてくれんし」。

だが平成12年、そんな父も心筋梗塞で他界。
「亡くなる前日も、翌日の段取りしとったのに」。
親子三人水入らずの海老せん作りは、たったの2年で潰えた。
「生地の味付けは母が分かっても、焼き方がわからんもんで。母がもう店畳もうかって。そんな時、魚市場の仲買いのおばちゃんから『お父さんなあ、本当はあんたに継いで欲しかったんやで』と聞かされて」。佐知子さんの瞳が不意に濡れた。
「父が亡くなる前日の、鉄板の温度設定だけを頼りに、何度も何度も失敗を重ねて」。
平成14年ついに先代の味を復活。

店の棚に「海老せんべい」が並んだ。
そして高校時代の同級生、幸弘さんと結婚し一男一女を授かった。
しかし喜びも束の間、その年の暮れ今度は母が末期癌に。
「病床で『もうこんなえらい仕事せんでいいから、側におって』って。でもここで店閉めたら、嫁に出たので浅井の名も絶やしたし、せめて両親との思い出が詰まった店だけは守らんとって」。
名代の海老せんべい作りは、アカシャエビの頭を手で落とし、専用機で殻を剥く作業に始まる。


次に馬鈴薯の澱粉、砂糖、塩と練り、鉄板で素焼き。それを3㌢ほどの棒状に切り、1日半乾燥させ冷蔵。
そしてその日に製造する分だけを取り出し、上から湯を掛け1~2日。
最後にもう一度鉄板で焼き上げれば、知多産アカシャエビだけを使った音羽屋の海老せんべいが完成する。
「暖簾はこの店と生きた、先祖の表札そのもの。だから私が頑張って守れば、きっと両親の供養になるはず」。
うら若き女将はこっそり瞼を拭った。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。