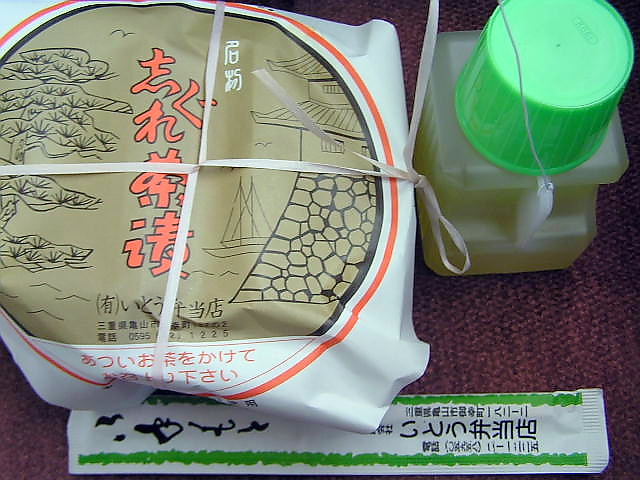今日の「天職人」は、愛知県新城市出沢の「養蚕農家」。(平成22年5月8日毎日新聞掲載)
小さな毛蚕のお蚕が いつの間にやら中指大 桑の葉抱えガジゴジと 「たあんとお食べ絹になれ」 蚕影明神おしら様 春蚕が嫁にゆく日まで 穢れも知らぬ白無垢の 真白き繭となるように
愛知県新城市出沢で大正時代から続く、養蚕農家三代目の海野久榮さんを訪ねた。

「真っ黒な1㍉ばっかの毛蚕が、5齢せると7~8㌢のドッチ(サナギ)になるだ。そいで2日も糸を吐きゃあ、真っ白な繭玉だわ」。久榮さんは、腰の桑摘み籠を外した。
久榮さんは大正14(1925)年、7人兄弟の長男として誕生。
「小学生になった昭和8年頃は、養蚕が大流行でのう。寺と商店以外、村のほとんどのもんが、養蚕せよっただ。輸出が盛んな時代やったで」。
尋常高等小学校を出ると産業試験場で学び、昭和16年に家業へ。
しかしその年も暮れ、真珠湾攻撃を境に日米が開戦。
絹糸輸出は中断、養蚕も衰退へ。
皮肉にもその前年には、養蚕業をさらに圧迫することとなるナイロン・ストッキングが、全米で発売されていた。
やがて日本は敗戦へ。
欧米では、化繊に押され絹需要が減退。
逆に国内では和服の需要が高まり、養蚕業も一旦活気を取り戻すものの、やがて中国、韓国からの輸入絹糸に押される憂き目に。
さらに昭和も50年代に入ると、和服離れが加速。
養蚕業全体が不況の澱みに呑み込まれた。
「まあ今残っとるのは、県内に2軒だけらあ。それでも今でも欠かさず36年間、家の繭を群馬県で絹糸にしてまって、伊勢神宮の天照大神に『三河赤引きの糸』として奉納せるだあ」。

久榮さんは昭和21年、近在からみつ子さんを妻に迎え、一男四女を授かった。
「一目見たとき、これだぞっと嫁に決めただ。それがもうはい孫が15人らあ」。
養蚕は、毎年5月5日の掃き立て(孵化した毛蚕を羽箒で新たな箱状の蚕座に移す作業)から10月初旬の桑の葉の終りまで。

掃き立ての日取りに合わせ、種屋が卵から毛蚕に孵化させた状態で仕入れる。
「種屋が卵をシート状の物に、均等に付着させて冷蔵せるもんで、それを『1枚くりょ、2枚くりょ』ってな感じて注文せるだ」。

1枚のシートには、卵が10㌘、約20.000匹の毛蚕となる。
その後、桑の新芽を2㍉ほどに刻んで与え、風通しの良い場所で飼育。

そしてサナギになるまで約1ヶ月(夏は20日)で5齢(5回の脱皮)し、丸2日糸を吐き続け繭玉となる。
「繭を作っとる時に揺すったると、鼻突きしてまって繭の内側が汚れてまうだ」。
こうして最高級品の三河赤引き糸が紡がれる。

「そんでも一向に相場は上がらん。昔っから米1俵が、蚕10貫目と決まってまって」。
だが夫婦は、お蚕様で5人の子を見事に育て上げた。
「娘4人の成人式には、家の2等や3等繭で晴れ着を拵えて」と、みつ子さん。
「私の晴れ着を、洗い直しに出して娘にも着せてねぇ」と、岡崎市に嫁いだ次女の直子さん。
「ほんでも汚れ落として洗ってまうだけで、4万円も持ってかれたらしいだあ」。
久榮さんの言葉に、親子水入らずの笑い声。
山鳥たちも釣られて鳴いた。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。