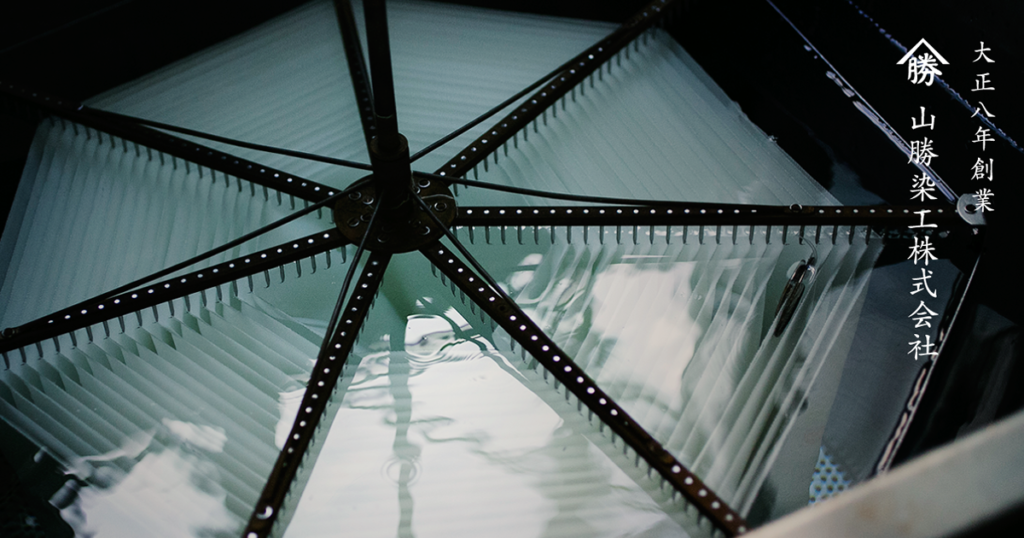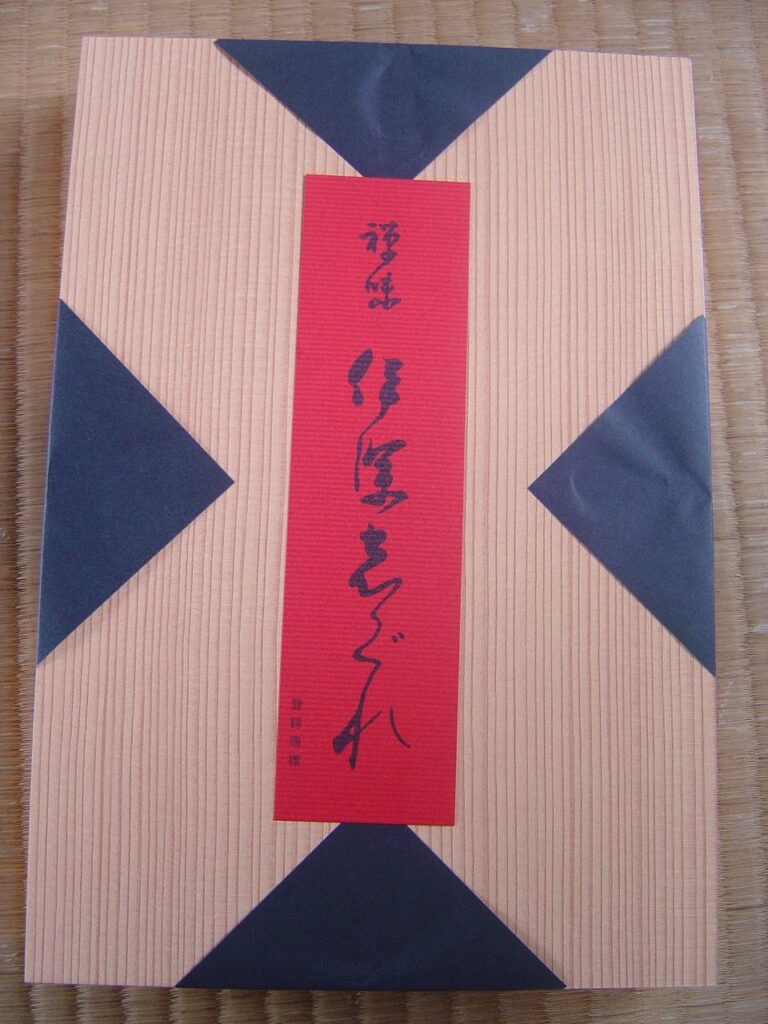今日の「天職人」は、名古屋市中区大須の「衣桁職人」。(平成23年2月26日毎日新聞掲載)
黒紋付の父と母 初の仲人大役と 父は祝辞を忍ばせて 空で何度も繰り返す 「時間ですよ」と急かされて 衣桁の羽織り取り上げて 二礼二拝の神頼み まるで鳥居か空衣桁
名古屋市中区大須で、明治34(1901)年創業の鈴木木工所。4代目衣桁職人の鈴木規夫さんを訪ねた。

呉服屋のショーウインドーをたまたま目にした折、何とも違和感を覚えた。
その正体が何であるのか、一旦気になると、もうどうにも居ても立ってもいられない。
何とかその正体を見破らんと、今一度呉服屋の入り口を繁々睨め回した。
すると晴れ着姿のマネキンに目が釘付け。
「間違いない、これだ」。
異様な波長の正体は、身動ぎ一つせず、瞬くこと無く商店街の通りを見詰めたままだ。
「そりゃあやっぱり呉服は、衣桁に掛けるのが一番収まりがいいですわ」。規夫さん)は、「まあ、お掛けになって」と、座面に帆布を張った胡床を広げた。

胡床とは、テレビドラマの戦国武将が、陣幕の中で腰を下ろす、一人掛け用の折り畳み式の椅子である。

規夫さんは昭和40(1965)年に、3人兄弟の長男として誕生。
「家がそのまんま作業場でしたから、子どもの頃からよく手伝ってました」。
大学院で建築設計を学び、設計事務所に勤務し一級建築士の資格を取得。
「学生の頃に清洲城や、セビリア万博に出品した安土城の設計を担当して。事務所に入ってからは、西尾城や寺社仏閣を手掛けました」。
それも縁か平成6年、西尾市出身の恵美子さんと結ばれ、一男一女を授かった。
その後30歳で独立し、寺社仏閣専門の設計事務所を開設。
「家業を手伝いながら自分の設計もしてと、二束の草鞋状態でした」。
平成15年、病の父を庇い、家業を継いだ。
「父が寝たきりになったから。父が永年勘だけで作って来た衣桁や反物掛け、胡床、几帳台などの木工品を、自分の手で一から合理的に設計しなおしたんです。私一人でも加工し易いように」。
衣桁とは、細木を神社の鳥居のように組んだ、高さ約1.7メートル、幅約1.8メートルほどの自立式木枠の着物掛け。
衣桁作りは、まず天棒となる洋材のラミンの丸棒に、臍穴を開ける作業から。そして両端に切込みを入れ、反り上がり部分の材を貼り付け磨き上げる。
次に縦棒の上下に臍を削り出し、中央の横棒用に臍穴を開ける。
そして下段の角材の面を取り、脚と共に縦棒用の臍穴を開け、漆仕立てに塗装すれば完成。

「組み立て式にしてありますから、使用時に組み立て、必要がなければ取り外して片付けることもできます」。
主に呉服屋、結婚式場、博物館、それに世界各国にある日本大使館などからも注文がある。
「和風旅館などでは、衣桁に呉服を掛けて、間仕切りとして利用されるようです」。
さらに施主の要望によっては、本漆仕立てや、天棒の両端に錺金具をあしらったり、蒔絵を施すものもある。
 写真は参考
写真は参考
衣桁と着物。
掛けると掛けられる関係は、一つになることで実用性を越え、室内を雅に彩る装飾品に生まれ変わる。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。