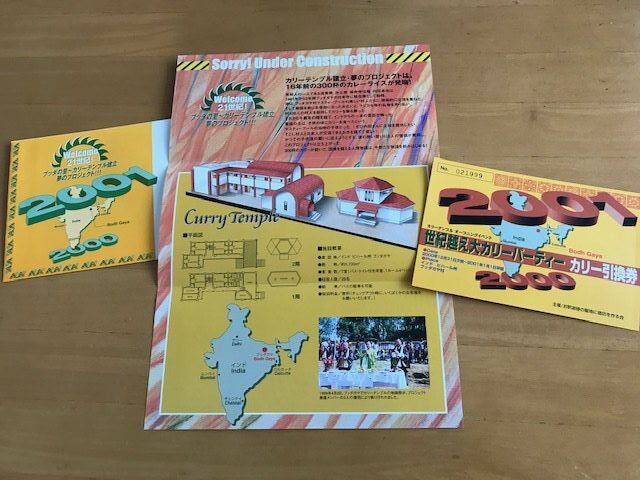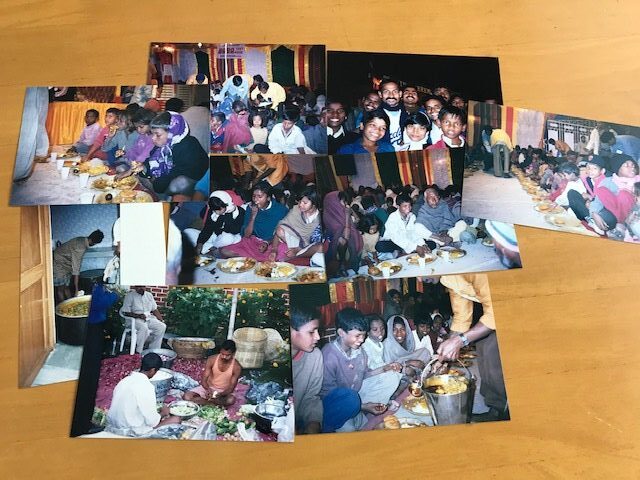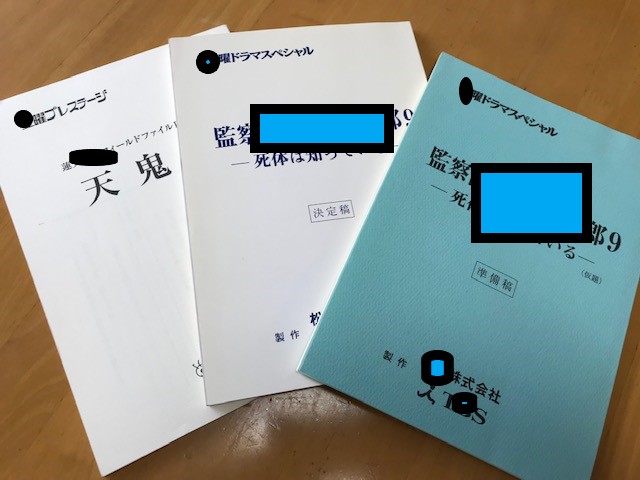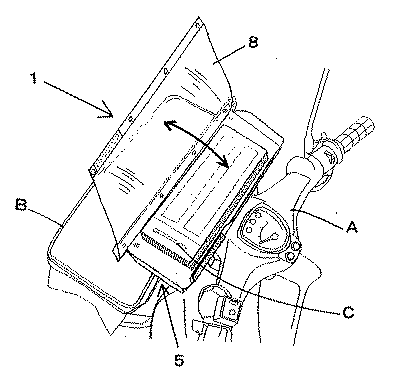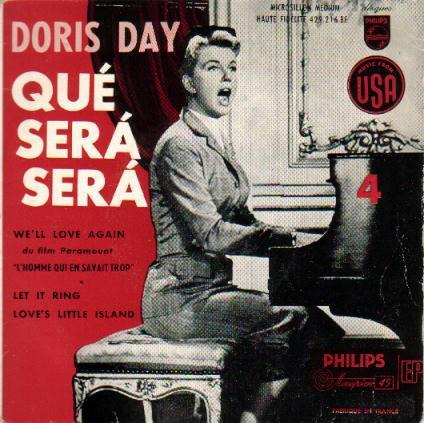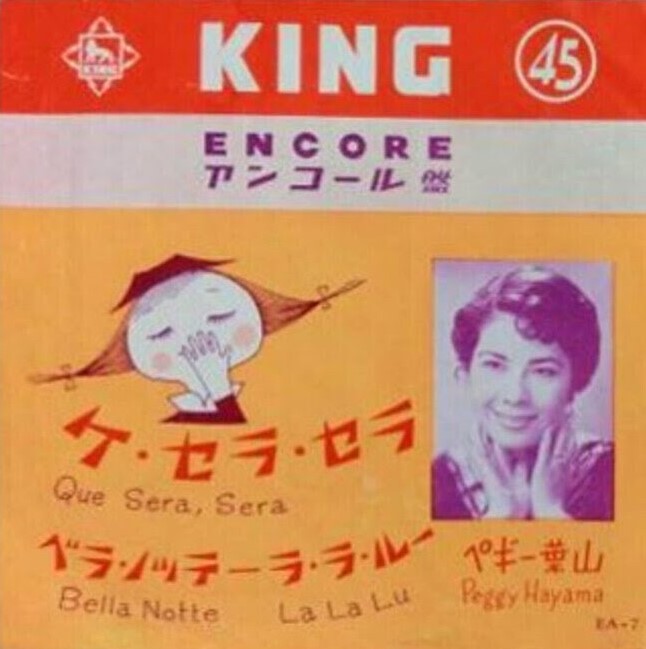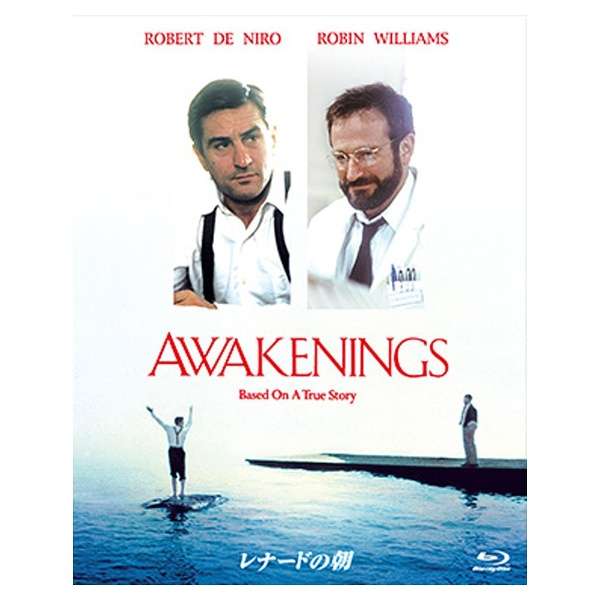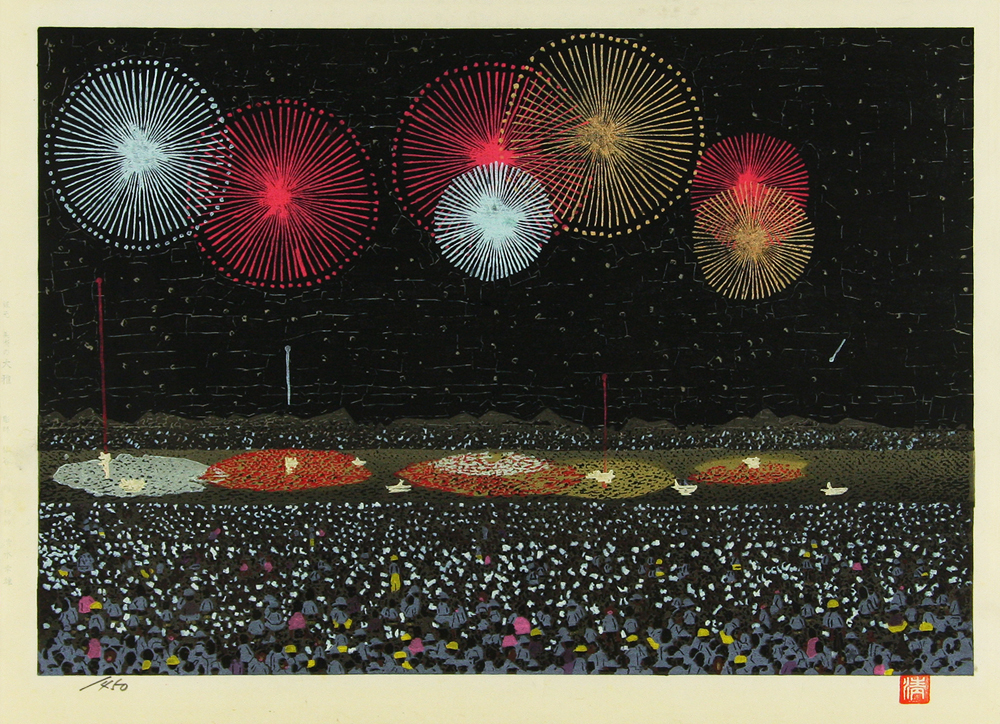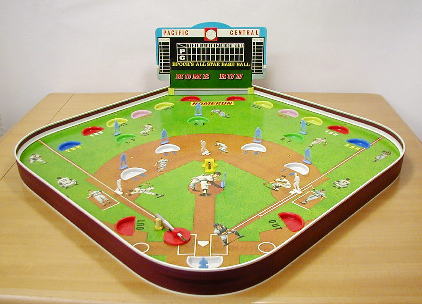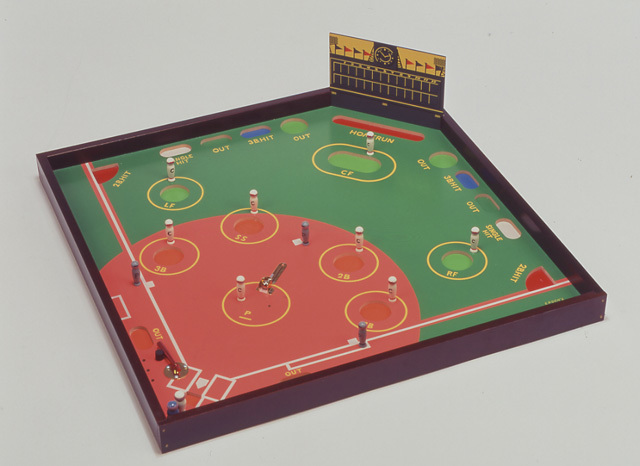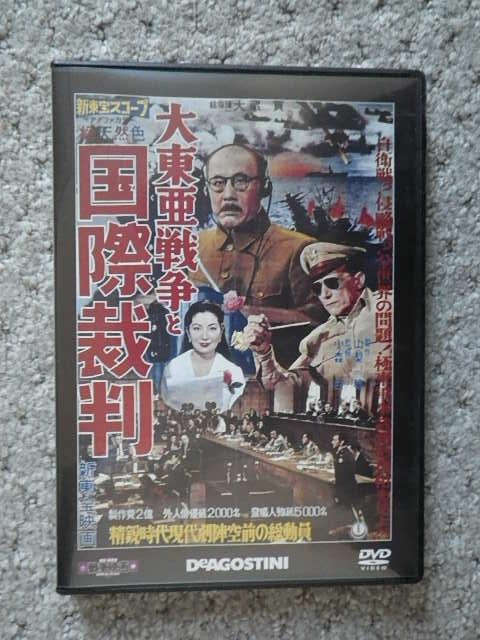「春になったら、奥飛騨でゆっくりと湯浴みして、高山の古い町並みでも漫ろ歩き、帰りがけに岐阜市美殿町のおきなや総本舗に立ち寄り、焼き立ての鮎菓子食べたいなあ」。

これが最後に届いたメールとなった。
2016年2月29日に、79歳でこの世に暇乞いされた、朝日新聞社四代目元社主の上野尚一さん。
入院先の病床から、ぼく宛てにお送り下さった、携帯メールである。
縁あってぼくは、上野さんの晩年、今を遡る10年ほど前から、岐阜県内各地をご一緒に旅して周った。
しかもそのいずれもは、時代の進化の影に消え入ろうとする、手仕事の職人ばかりを訪ねる旅。
「仙人。今度は、君の本に書かれている、高山の銅職人を訪ねたい」と言った調子で。
仙人とは、在り難くも上野さんから賜った、ぼくの渾名だ。
何故仙人かと言うと、当時ぼくは毎日新聞で毎週「天職一芸」と言うコラムを連載しており、仙人ならぬ千人の「天職人」を追って取材していたからである。
上野さんは、拙著「百人の天職一芸(風媒社刊)」「東海の天職一芸①~③(ゆいぽおと刊)」を熟読され、次なる岐阜への旅を計画されたものだ。
一昨年。
高山からの帰路、郡上へ抜けるせせらぎ街道。

新緑のトンネルを走り抜けながら、あまりの清々しさに、ぶらりと道の駅に立ち寄った。

「美味いなあ!」。
揚げたての飛騨牛コロッケを頬張り、上野さんが唸った。

「こんな風にベンチに腰掛け、コロッケに舌鼓を打つなんて、子どもの頃以来だよ」。
懐かしそうに、子どものような目で、遠くの山並みを眺めた。
「こんな澄んだ空気の中でいただくコロッケは、何より美味しいご馳走だよ」。
たかだか1個200円にも満たぬコロッケ。
ぼくから見上げれば、雲の上のそのまた上の、近寄りがたい名家のお方。
しかしその時ばかりは、地位も肩書も脱ぎ捨て、何一つ俗世のしがらみの無かった、子どもの頃と同じ一瞬を、堪能されたのかも知れぬ。
間もなく上野さんがこよなく愛した、おきなや総本舗の鮎菓子が、今年も販売される。

そしたら上野さんの遺影に、いの一番で焼き立てをお供えするとしよう。
合掌
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。