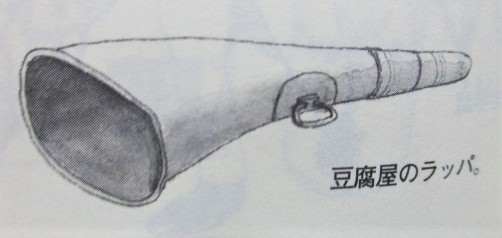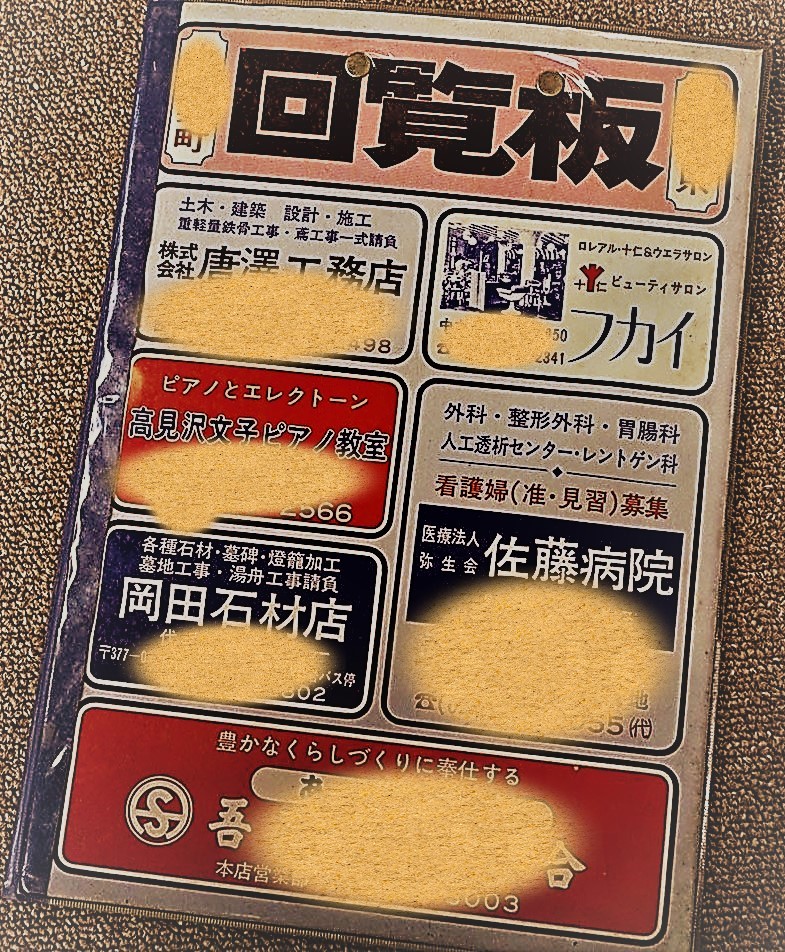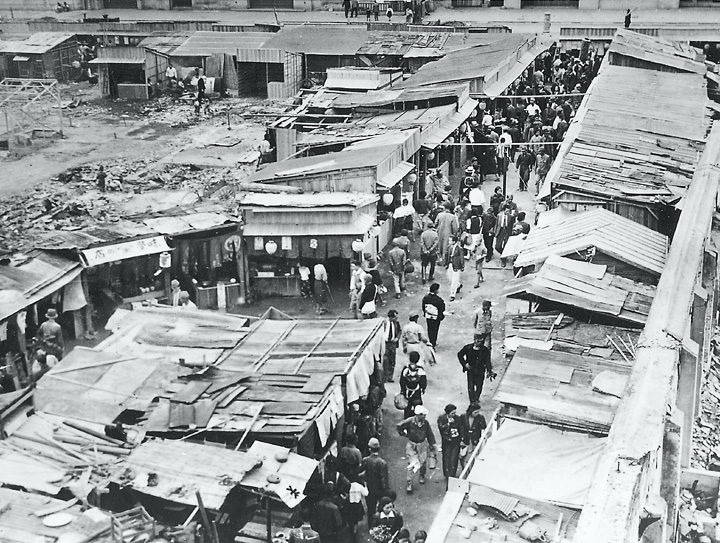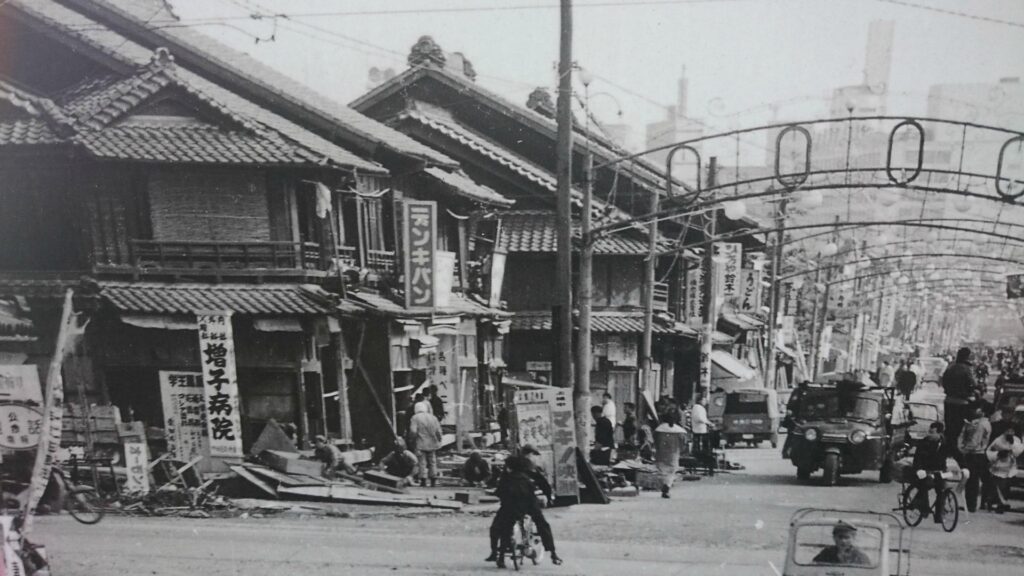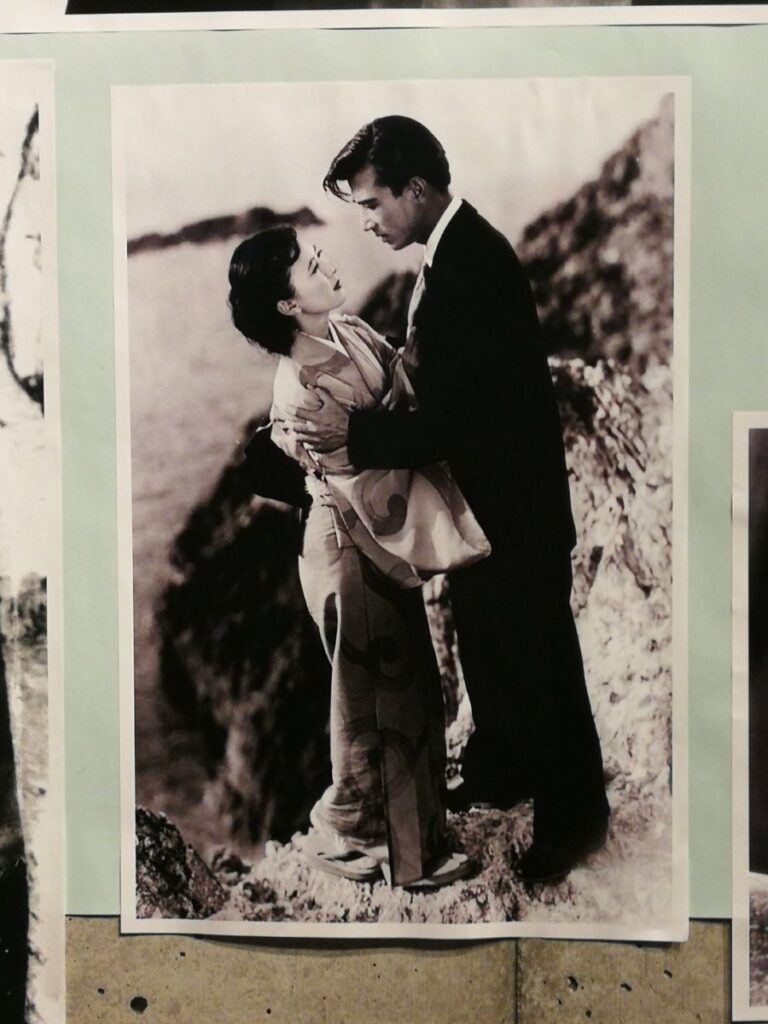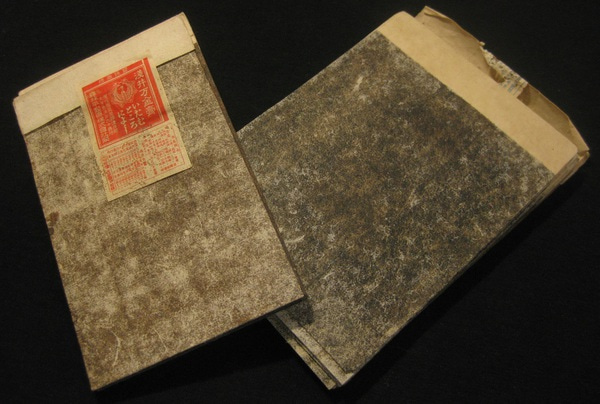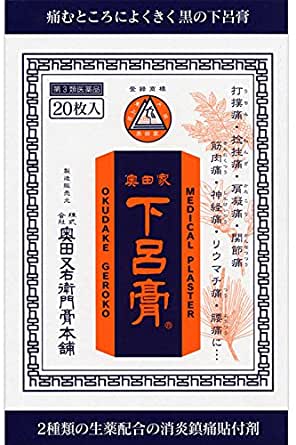両親は岐阜県海津市南濃町の高台で、今も安らかに眠る。
眼下には木曽三川の大河。
その先には、広大な濃尾平野を望む。

何もこの地に、特別なご縁があったわけでもない。
それが証拠に、母は鹿児島生まれ、父は三重生まれである。
ましてやぼくが生まれたのは、名古屋の端っくれ。
しかし母を亡くした翌年。
まるで何かに誘われるかのように、ぼくはこの地を墓地とした。
振り返れば当時の父は、頼りにしていた母が、自分を残し先に世を去ったことを儚み、投げやりだったのだろうか。
何かに付け「お前がそう思うんやったら、わしもそれでええ」と、そんな調子。
程なく斑の認知症と診断された。
だから墓地を決めるにしても、既に父は彼岸と此岸の境を、彷徨っていたのだ。
子どもの頃、墓参りと言えば、それは三重の山奥の、父方の祖先の墓参りを指した。
幼心にも不思議に思い、ある時母に尋ねた。
「お母ちゃん家の、お爺ちゃんのお墓へは、何でお参りに行かんの?」と。
すると母は気まずげに「鹿児島までは遠いし、お爺ちゃんの墓参りはせんでええ」と。
これは母の夜伽の席で叔父から聞いた話だ。
=戦時中に生みの父を亡くし、後に婿入りした養父と折り合いが悪く、散々いじめられた。
そして戦後の娘時代、将来を誓うほどの恋仲を、引き裂かれたようだ。
それがきっかけで、一宮の繊維産業に職を求め、この地へ舞い降りた。=
だからぼくが大人になるまで、母は一度たりと故郷鹿児島へ帰らなかったのか。
しかし遺品のアルバムから、最晩年の両親が桜島をバックに、満面の笑みを浮かべる写真を見つけ、少しホッとした。

それは母の納骨を済ませた、間もない頃のことだ。

「お母ちゃん、見えますか?今から260年もの昔。丸に十の字を背負った、あなたの故郷の薩摩藩義士が、己が身を楔に護岸を築き、水害に苦しむこの地の、尊き民の命を救った、そんな気高き薩摩恩顧の地が…」

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。