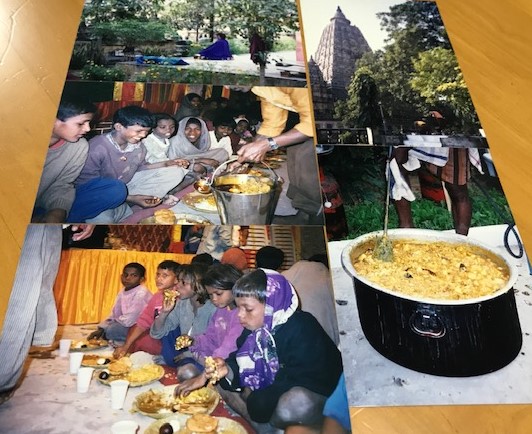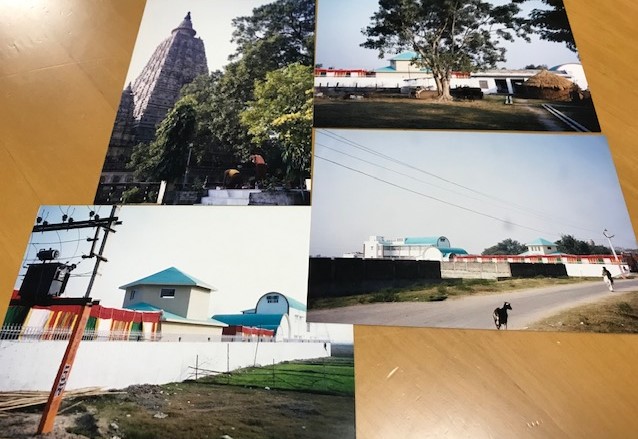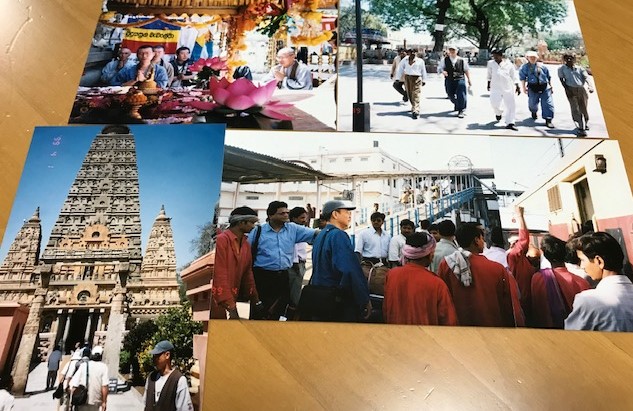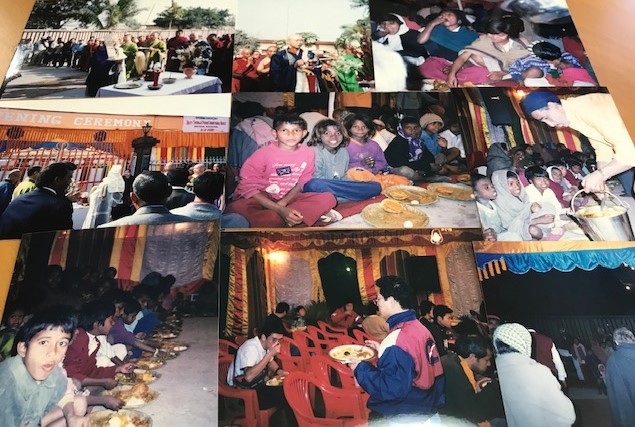『犬好き親子は、わん!ダフル?』
2005.夏 季刊誌掲載
「わんわんわん!」「クゥ~ン!」「ウォン!」「キャィ~ン」。
360度の大パノラマで、犬たちが歓迎の鳴き声を上げる。
「これで犬の言葉が理解出来たら、楽しいのになぁ」。
犬好きのぼくは、取材の事などすっかり忘れ、もう無我夢中。
ここは春を待ち侘び続けた、岡崎市大平町のわんわん動物園。

「ああ~っ!」。
少年が駆けだした。
岡崎市立藤川小学校3年のK.A君だ。
「K君!」。
お母さんのY子さんの声など、耳に届くはずもない。

「お母さ~ん!ねぇねぇ、見て見て!ボルドーマスティフのジャイだって!大きいよ!」。
K君の家は、家族揃って大の生き物好きとか。
ミニチュアダックスのレオ君は3歳。
まだまだヤンチャなお年頃。
それに8ヶ月になる、亀のピエール。
「???」。
『なんとも洋風な亀だなぁ・・・』。
一瞬そう思ったぼくの心を、見透かされたのか「本当はママ、ペ・ヨンジュンって名前にしたかったんだよ!」と、小声でこっそり教えてくれた。
『なんとも大胆な!』。
亀に人格など無論ないが、それにしたって・・・せめて亀格くらいはあるのやもしれぬ。
だとすれば余りにも身勝手甚だしい、人間の傲慢さが闊歩した命名となってしまうではないか!
しかしお母さんときたら、まったく意に介していないご様子。
「わたし海と山に囲まれた、長崎育ちだから。自然が周りに一杯で」と。
これまでのペット歴は、犬5頭に猫10匹、それにインコとウサギとか。
「動物と目が合うと、もうその場に釘付け」。

そう言うお母さんの言葉尻から、K君は大型犬の金網の前で、ディアーハウンドのガディスとアイコンタクト中。
もう何人たりともこの親子を止めることなど出来ぬ。
この楽園の主たち、137種300頭すべての犬たちを、とことん制覇し尽くすまでは。
なんとも微笑ましい限りの仲良し親子。
両手一杯に犬たちのよだれがねっちょり。

だがそんなことなど一向にお構いなし。
大の犬好き親子は、わんわん動物園の隅から隅まで、虱潰しに歩き回り、ゲージの前に立ち止まっては片っ端から犬を撫でまわす。
まるで散歩の途中、犬が片足を上げ自分の縄張りを主張する、マーキング行為そのままに。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。