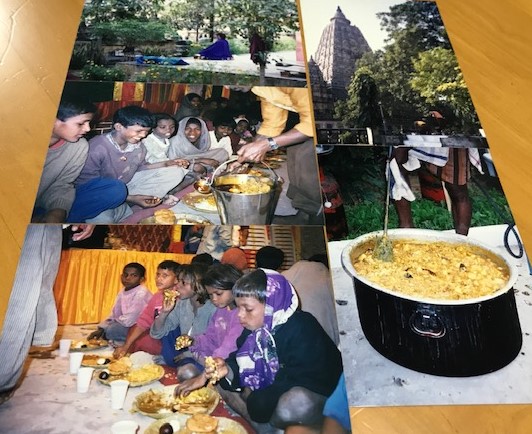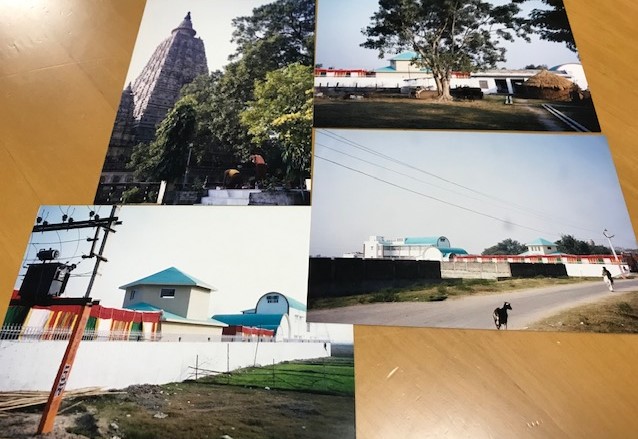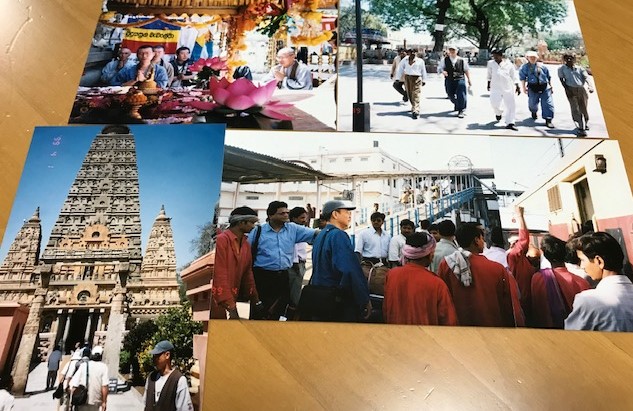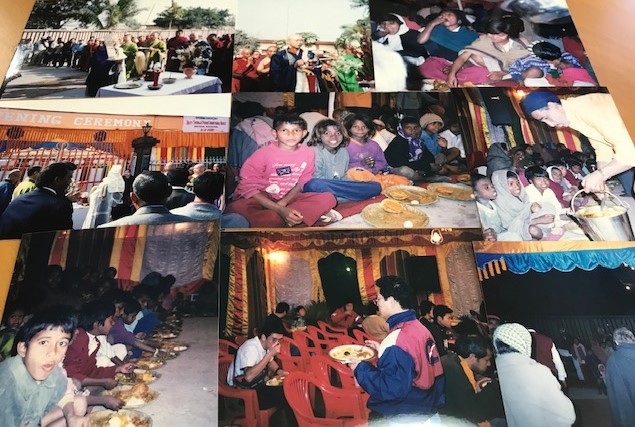『馬耳東風でストレスフリー!』
2005.冬 季刊誌掲載
「『天高く馬肥ゆ』『秋茄子、嫁に食わすな』ってかあ!」。
抜ける様な青空を見上げ、夏の間に調子をこいて飲み過ぎたビールの祟りか、ポッコリ迫り出たお腹をポ~ンと一叩き。
その小気味いい音に、馬場をゆっくりと巡る馬も慌てて「ヒヒ~ン」といなないた。
抜ける様な秋晴れの下、悠然と馬場を巡るサラブレツドやアングロ・アラブ種の馬たちを眺めていると、長閑な風情が満喫できる。
がしかし、そんな長閑さを嘲笑うかのように、引っ切り無しな車のエンジン音が背後で行き交う。
それもその筈、ここは泣く子も黙る交通量の多い国道248号線。
まるで荒れ狂う大河の流れのように、猛スピードで車が行き交い、静かな田園風景の残る額田郡幸田町を南北に貫く。
今回ぼくが訪ねたアオイ乗馬クラブは、けたたましくノイジーな国道脇に、まるでポッカリ口を空けたオアシスのようだ。
どことなく漂うノスタルジックでウッディーなクラブハウス。

すぐ隣には、11頭の馬たちが一列に並ぶ厩舎が続く。
オーナーの花井さんご夫婦に伴われ、厩の中へと。
愛くるしい真っ黒な20の瞳がぼくに向けられた。
「ちょっと待てよ!」。
「11頭いるんだから・・・瞳が2個足りなくない?」。
「ああぁ、馬にもいるんだ。ぼくのように臍曲がりなヤツが!」。
10頭の馬たちとは異なり、頭と尻が逆向きになった馬が1頭!
長く真っ白な尻毛を、時折りブラ~ンブラン。
「芦毛のサラブレッド、騙馬(せんば)のメリーって言うだぁ」。
芦毛とは白毛。
騙馬とは、去勢した牡馬(ぼば)の呼び方とか。
「ええっ!じゃあ、サラブレッドのニューハーフってぇこと?」と、思わず囁いてしまったぼくの言葉が聞こえたのか、花井さんが付け足した。
「若い頃、気性が荒かったり、悪癖が強かっただなぁ。だで玉を抜かれただ」。
競走馬としての人生を7~8歳(人間に当てはめると25~26歳)で終え、花井さんの元で第二の人生、もとい「第二の馬生」を送る馬たち。

「ここで20年近くを過ごし、天寿を全うする馬たちは幸せもんだて」。
ここを訪れる馬たちは、競馬新聞にも掲載されるレース・ネームが名付けられている。
まるで瞬くネオンの下で、怪しく咲くニューハーフの源氏名のように。
「だもんでぇ、第二の人生に相応しいよう、わしらや常連さんらで新しい名前を付けたるだぁ。なぁ」。
花井さんは、愛妻のはな江さんを見つめた。
「ちなみにこのメリーは、ここに来てからの名前。昔の名前は『パルフェ』だったの」。
はな江さんは、メリーの大きくて長い鼻筋をやさしく撫で付けた。
「最初っから真っ白じゃないだわ。生まれたては、みんな真っ黒か茶色。ほんでもって3~4歳になって芦毛にだんだん生え変わってくるだぁ」。
中でも一番の凛々しさは、黒鹿毛の四白(よんぱく)流星とか。
黒鹿毛は、黒味のある鹿毛。
四白とは、蹄の上の毛が10cmほど、白足袋を履いたような4本脚を指す。
流星は、眉間に浮かぶ白い菱形状の毛が、鼻筋を流れる様に気品溢れる毛並みとか。
いずれの馬たちも、アスリートとしての現役時代を終え、花井さん夫婦の元で穏やかな第二の馬生を謳歌している。
「大きな大きな子供さんたちに囲まれ、幸せですねぇ」。
思わずぼくがひとりごつ。
すると。
「この子らは、人間と違って文句一つ言わんらぁ」。
花井さんがメリーのたてがみを撫で付けた。
「馬は人の気持ちが良くわかる生きもんだもんで、瞳と瞳で意思を伝えあうだ」。
はな江さんがメリーの瞳をやさしく見つめた。
メリーは馬耳東風そのままに、我関せずで飼葉を旨そうに食べ始めた。
これからはぼくも、メリーたちのように、煩雑極まりない世事に振り回わされたりせず、都合の悪い事はみんな「馬耳東風」で生きて見るか。
ストレスフリーな生き方こそ、贅沢極まりない生き方に違いないから!
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。