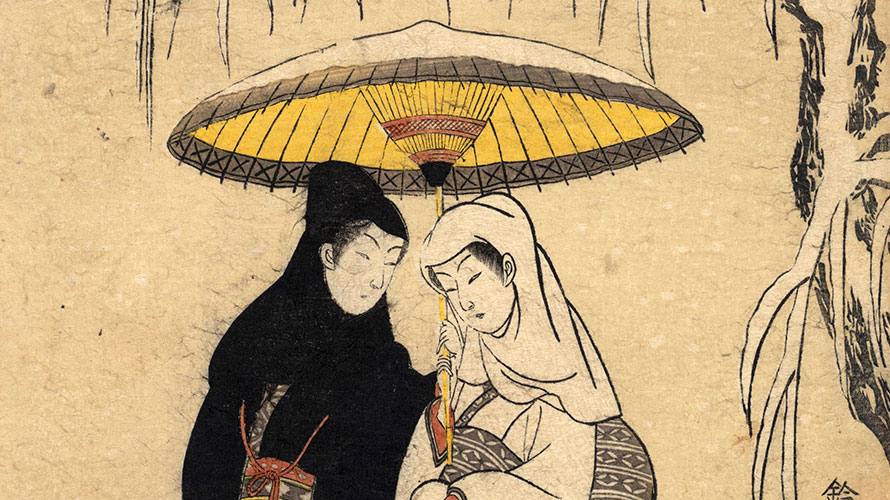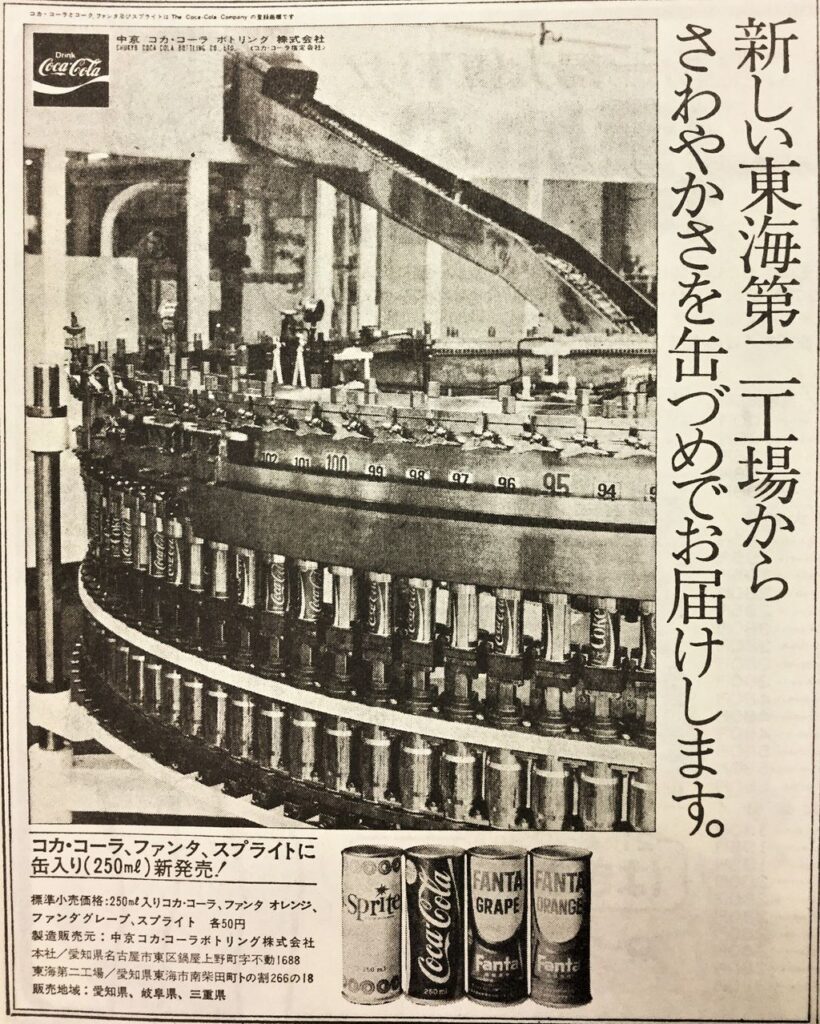「素描漫遊譚」
「社会人野球の監督だぁ!」
「ゲームセット」。
ベンチからグランドに一歩踏み出し、帽子を取った白髪の背番号30番は、深々と頭を垂れた。
愛知県東海市の硬式野球チーム・東海REX監督のY.Tさん(66)だ。
 写真は参考
写真は参考
「グランドに一歩入ったら、そこは修行の場だでな。礼に始まり礼に終わる」。
日本で3番目に高齢な日本選手権優勝監督は、白い歯を見せて穏やかに笑った。
この東海REXは、旧新日鉄社会人チームであったが、九州八幡製鉄の野球部が廃部に追い込まれる中、企業・自治体・民間の協力を得て、昨年1月に社会人広域チームとして生まれ変わった。
 写真は参考
写真は参考
「たった15人だけのヘボチーム、端から引き受ける気なんてなかったて」。
しかしもう一度ユニフォームを着たい。
そんな想いが、グランドに半世紀を賭けた男の魂を衝き動かした。
「やっぱりユニフォーム着ると、歳忘れるねえ。まあ俺にとっては、これがスーツだでな。それに子供たちから、エネルギー貰らっとるしな」。
終戦後、疎開先から名古屋市天白区の生家に戻った監督は、布を繋ぎ合せて作った粗末な手袋型のグローブで「野球ゴッコ」に高じた。
「野球馬鹿の虫があったんだろうな」。
小学4年の時、叔父から譲り受けた古い皮のグローブを手に、野球部へ入部。
半世紀以上の野球人生が、プレイボールとなった。
中学3年の2学期、東邦高校野球部監督の目に止まり、東邦中学に編入し公式野球部へ。
甲子園の晴れ舞台を目指し、名門中京商業とも互角に渡り合った。
その後、社会人野球の製鉄釜石に所属し、グランドに数々の名プレーを刻み込んだ。
25歳の年に、幼馴染のK子さん(67)を妻に迎え、釜石での新婚生活が始まった。
翌年には長女が誕生。
昭和41年(1976)、生後間もない次女を伴い、東海市の新日鉄社会人チームに移籍し、コーチ兼キャプテンに就任した。
 写真は参考
写真は参考
30歳の若さで監督へ。
「息子だったらなあ。キャッチボームでも出来たんだろうが」。
野球一筋に打ち込むあまり、二人の娘を何処へも連れて行く暇さえない。
幼い娘達の元へは、義理の弟がよく遊びに訪れていた。
しかし監督は朝から晩まで野球。
「あの頃、よう女房が嘆いとった。『あそこの旦那は、野球やっとるわりに小さな人だね』と、近所で噂されて困ると」。
しかしそうは言うものの、半世紀以上に渡り夫のユニフォーム姿を支えた妻は、家庭と言うベンチで家族の生活に采配を振るった。
「歳喰う毎に不思議なもんで、段々女房孝行するようになってきた」。
日焼け顔が思わず綻んだ。
「4年生になる孫がおるんだが、これがサッカー少年でな。やっぱり今時の子だでなあ」。
寂しげな言葉を、監督はポトリと落とした。
「でもこの前、グローブを持って遊びに来て『お爺ちゃんキャッチボール教えて』と。娘に吹き込まれたんだろうか。ちょっとだけスナップ効かせてやったら、『お爺ちゃん凄い』だと。これまでの野球人生の中でも、一番嬉しいひと時だったかな」。凄みを放つ強面の顔が、一瞬好々爺の表情に挿げ変わった。
 写真は参考
写真は参考
無心でひたすら白球を追いかけた55年の歳月。野球人生に何も悔いはない。内野の要、ショートを守り抜いた監督のグローブは、髪に白髪が目立ち始めた初老の妻の心を、今はしっかりと受け止めている。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。