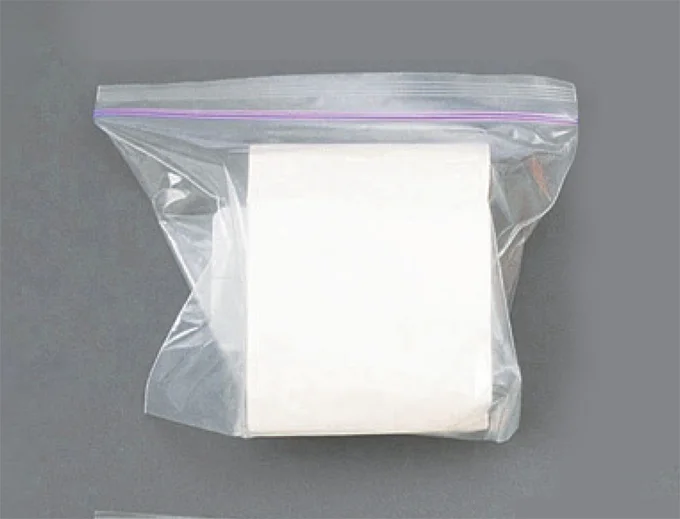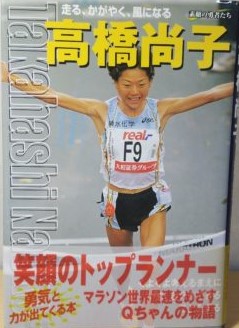「素描漫遊譚」
「岐阜の全日本実業団対抗女子駅伝競走大会」
岐阜の師走。
寒風を切り裂いて駆け抜ける、華麗なアスリートたち。
金華の麓から大垣を経て、再び岐阜城を仰ぎ見ながら喝采を目指す。
 写真は参考
写真は参考
沿道に幾つもの感動と興奮を振りまき、アスリートたちは白い吐息だけを風に躍らせ、ひたむきに走り抜ける。
今年もまた数々の名場面を刻んだ「第24回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会」の、スタートを告げる号砲が鳴り響く。
「何でこんなに苦しい想いをしてまで、走らなきゃなんないの?」。
運動音痴のぼくは、毎年冬が大嫌いだった。
いや、冬そのものを疎ましく想っていたのではない。
厳密に言えば「冬のマラソン大会」って奴が苦手で、何とも忌み嫌っていたのだ。
だから毎年決って「マラソン大会」の前日には、咳き込んだり熱が出て、公然と病欠の勲章を得て、まんまと敵前逃亡を決め込んだりした。
毎年その技術は巧妙化し、6年生の頃にはすっかり、自らの体調を見事なまでにコントロール出来るほどの腕前となった。
今考えてみれば、それほどのセルフコントロール力があったなら、何故もっと他に有意義な使い道を考えられなかったのだろう。
ともかくマラソンだけは、ご免被りたかったのが本音である。
「尚子は親思いやったでね。中学の部活で陸上部を選んだ時も、靴の他に何にも道具揃えんでいいからって」。
岐阜市大洞緑山の高橋良明さん(63)は、部屋中Qチャンの写真に囲まれた応接で、穏かに笑った。
 写真は参考
写真は参考
この御仁こそ、2000年シドニー五輪の立役者の一人、女子マラソン金メダリストに輝いたあの高橋尚子さんのお父上だ。
それが証拠に、シドニーを駆け抜けたマラソンシューズと、強豪シモンを交わして抜きん出た際に、沿道へ放り投げたあのサングラス、それに国民栄誉賞の大きな盾が、サイドテーブル上に無造作な状態で置かれていた。
 写真は参考
写真は参考
こうお膳立てが整ってしまえば、後はもうQチャンの生い立ちに迫るしかない。
高橋父は、昭和39年(1964)春に、岐阜県清見村の小学校で教壇に立ち、2年後に岐阜市内の小学校へと転勤。
翌、昭和42年(1967)に同僚の紹介で中学校教諭の滋子さんと結婚。
昭和44年(1969)に長男を、そして昭和47年(1972)5月に尚子さんをもうけた。
「普通に元気な子やったね」。
もっと激的な初対面かと思いきや、何のことはない極々ありふれた父と娘の逢瀬だったとか。
両親共に教師の聖職。
当然教え子への愛が優先し、我子の子育てには犠牲も生じた。
「私が忙しかったから、尚子は早くから精神的に自立していたわね。遠足の準備も早くから計画的に済ませるような」と、高橋母。
本を読むにしろ、絵を描くにしても、ピアノの練習でも、とにかく自分が納得するまでやめようとはしない。
Qチャンはそんな少女だった。
中学で陸上と出逢い、走る道に進みたくて岐阜県立岐阜商業へ。
「かけっこやっとっても食べてけんで、教員免許を取ってこい!」。
高橋父の言葉に従い、商業高校の教員免許を取得。
次いで大阪学院大学へ。
4年の時、リクルートの北海道練習に加わったことで、小出監督と運命的な出逢いが。
やがてシドニー五輪へと、夢のエスカレーターは頂点を目指して昇り始めていた。
「ちょうど34.5㌔地点やった。シモンと競り合う尚子の姿が見えたんやて。尚子側の歩道は、木陰で涼しく黒山の人だかり。私らが見守るシモン側は、カンカン照りの人気なし。尚子は私に気付いて、サングラスを渡そうとしたんやて。そのためにはシモンの前に出るか後ろに下がるかしないと、シモンを越えてサングラスを放れんかったんやて。それで尚子がスパートをかけて、シモンを抜きサングラスをよこして、そのままゴールに向かったんやて」。
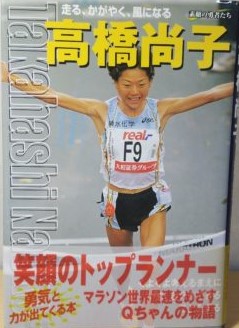 写真は参考
写真は参考
高橋父は、スタジアムを目指したが、黒山の人だかり。
スタジアムから歓声が上がった。
「ああ、誰かがゴールしたんや」。
スタジアムで喝采に包まれていた主が、自分の愛娘だと知ったのは、同じ観戦ツアー客からの携帯電話だった。
『さぞや感動の表彰式だったですね』と尋ねた。
「何が何が。もうその頃私らツアーは、バスで移動中。娘がゴールドメダルをもらっとる時に、私らはゴールドコーストへ向かっとったんやて」。
高橋父母が、金メダリストの娘とご対面するのは、それから1ヶ月も先。
羽島駅でこっそり「世界の尚子」を迎えた。
親子水入らずの夕餉は、Qチャンの好物という筑前煮と、たっぷりのゴマ油で炒った野菜一杯のオカラだったとか。
 写真は参考
写真は参考
「今でも帰って来ると、ちゃんとお手伝いしてくれるの」と、高橋母。
両親の願いは、Qチャンのロマンチックな人生のゴールだ。
Qチャンは永遠に、自分の描くゴールに向け、今日もひたむきに走り続ける。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。