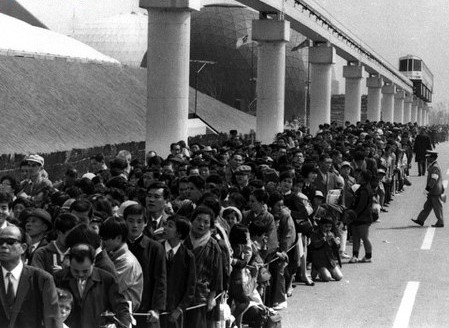「素描漫遊譚」
「昭和への憧憬」
「サツキとメイの家」は、タイムマシンの入口だった。
少なくとも昭和32年生まれのぼくにとって。

エイジングと呼ばれる経年変化加工技術で、見事に再現された「サツキとメイの家」のあちらこちらから、もうこの世にはいない父と母が、まるでぼくに呼びかけてくるような不思議な錯覚に陥った。
ついこの前の時代なのに。
もう手の届かない場所にいってしまった、途方もなく遠い時代のような気がする。
思わず耳を澄ましてみる。
「もう!また宿題もせんと、遊び呆けて!」。
でもお勝手の奥から、大好きだった母の声はもう聞こえない。
どうしてぼくは、こんなに遠くまでやって来てしまったんだろう。
大人になるのと引替えに、ぼくは一番居心地の良かった時代に別れを告げた。
誰もがそうであるように。
本物のサツキとメイの家があった時代に、ぼくだけこっそり止まっていられたら、どんなに幸せだっただろう。
つぎ当てズボンに、黄ばんだランニングシャツ、黒ずんでつま先の破れたズック靴でも十分だった。

いつもこめかみにサイの目大に切ったトクホンを張り、不規則な醤油の染みの模様が入った割烹着。
首には酒屋の名入り手拭を巻き付け、細かな内職仕事に目を落した母。
お勝手の七輪からは、煮物のやさしい匂いがする。

それでも母は、ぼくが玄関の引き戸を、そ~っと音を立てずに開けようとするだけで、「お帰り!」の一声を浴びせた。
まるですべてが、お見通しであったかのように。
人は誰のために大人になるんだろう。
どうして居心地の良かったあの頃に、止まっていられないのだろう。
時代はあまりにもけたたましい速度で駆け抜け、人が人としてごく普通にやさしくいられた時代をも、通り越したのだろうか?
だからお金を払わなければ、癒されないような時代を迎えたと言うのか?
戻りたくても、もう戻ることの出来ない昭和。
そして父と母の温もり。
家族たったの三人、丸い座卓で倹しい食事を囲んだあの頃が、ぼくにとって身の丈サイズの幸せな時代だった。

出来ることなら、エイジングで父と母をも再現して欲しかった。
「サツキとメイの家」は、あの頃の我が家なんかより、遥に上流家庭に見える。
それでも、大好きだった昭和と言う時代の中へと、一瞬ではあってもぼくを連れ帰ってくれた。
ありがとう、サツキとメイの家。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。