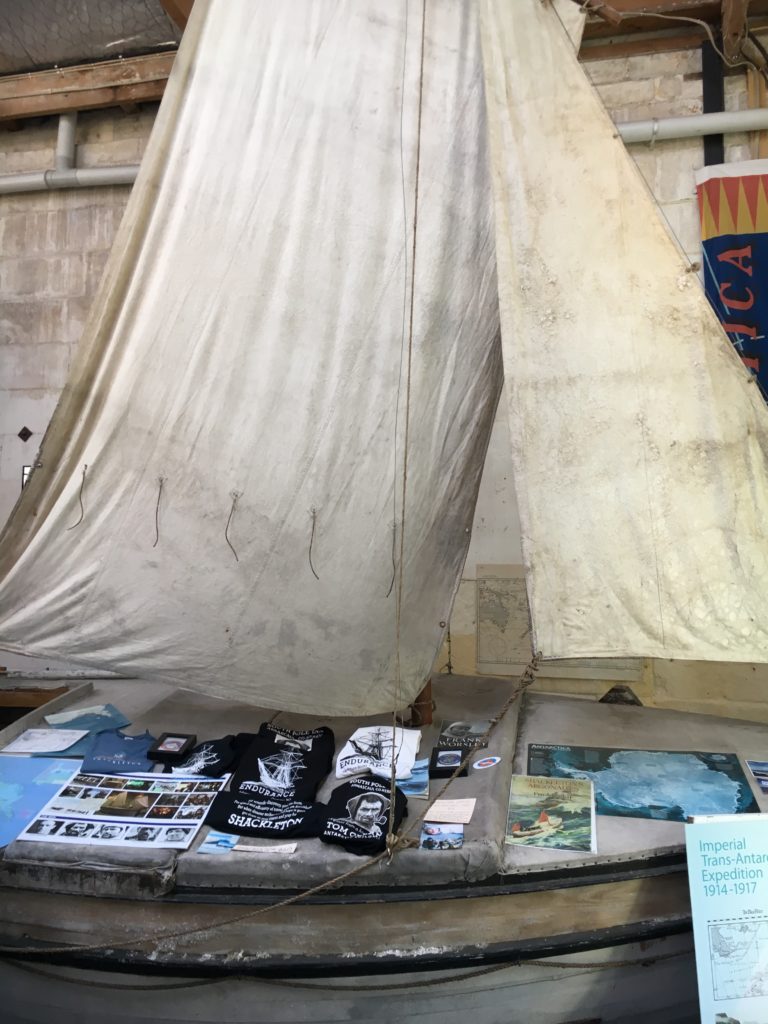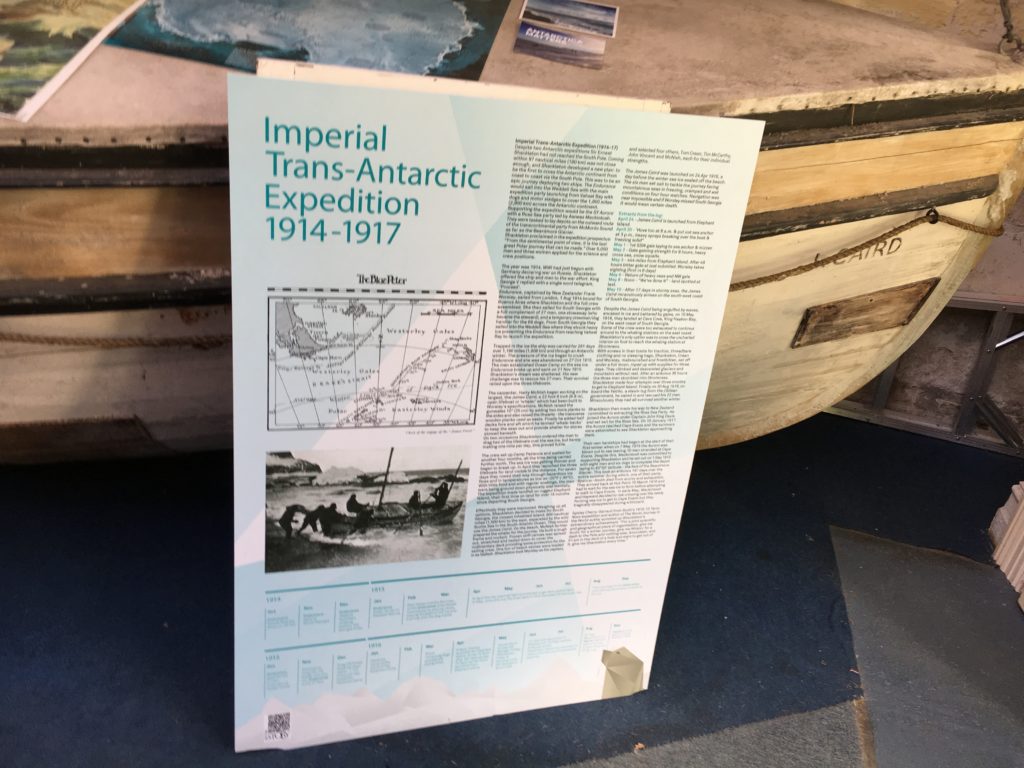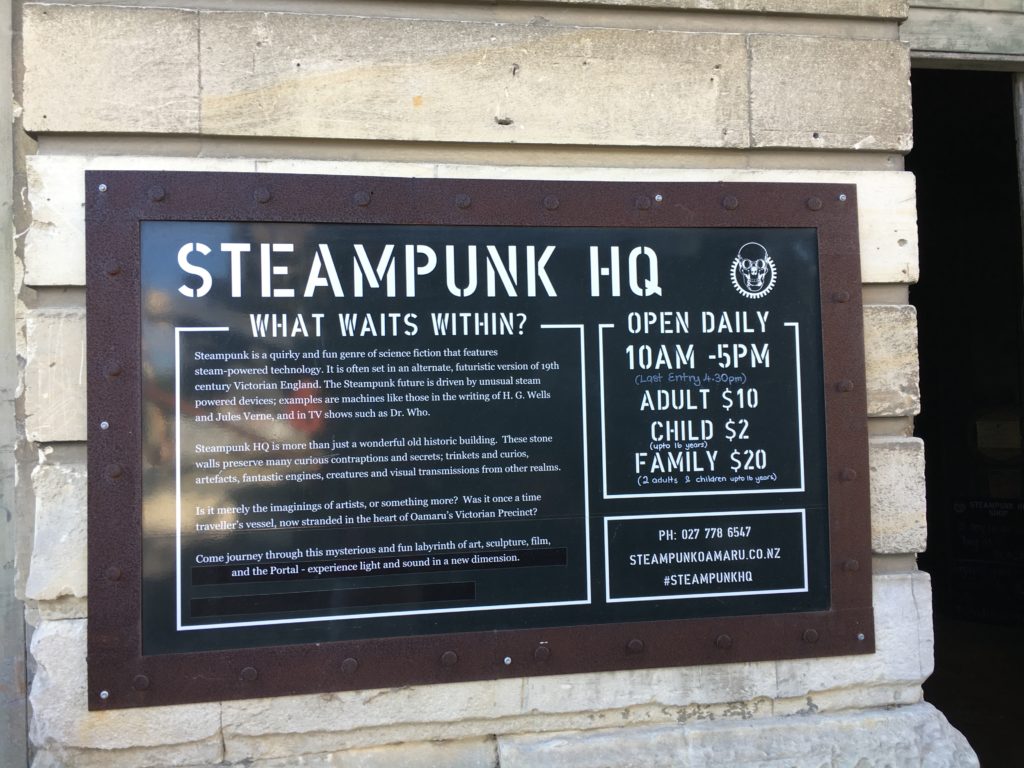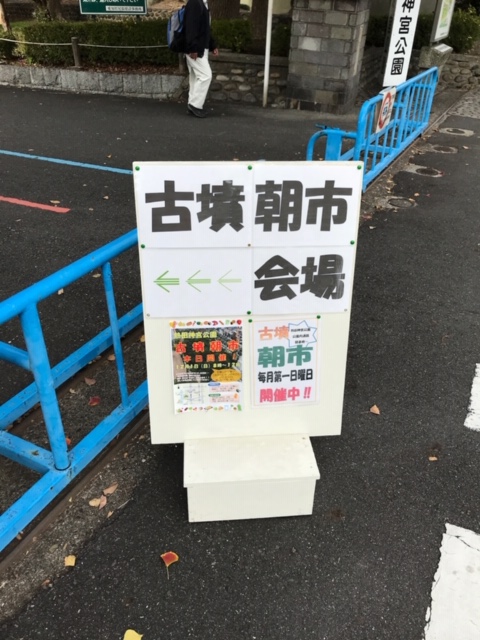今夜の弾き語りは、今年2月のぼくのリサイタルで披露いたしました「雪花火」をお聴きください。
奥飛騨温泉の露天風呂にでも浸り、こんな風雅な一夜を過ごすことが出来たら、さぞかし素敵だろうなと、そんな風に幻想したイメージを、「夏花火」のメロディーにのせて歌詞だけ書き下ろした作品です。
「雪花火」
詩・曲・歌/オカダ ミノル
雪見格子に燻(くゆ)る湯煙 盆を浮かべてふたり酒
髪を束ねた湯浴み姿の 君の項(うなじ)に雪が舞う
冬の砌(みぎり)の雪闇割いて ヒュールルと鳴いて舞い上がる
まるで春待つ雪割草か 凛(りん)として気高い 雪花火
雪見格子に跳ねる影絵は 君が描きし雪兎
ポッと紅挿す君の頬 まるで一葉(いちよう)の浮世絵か
冬の砌の雪闇突いて ヒュールルと咲いて闇に融ける
まるで春待つ雪割草か 凛として気高い 雪花火
冬の砌の雪闇割いて ヒュールルと鳴いて舞い上がる
まるで春待つ雪割草か 凛として気高い 雪花火
これまでの人生で、二回だけ雪が深々と降り積もる中、露天風呂に入って、落ちては湯船に溶け入る雪を、飽きもせず眺めていたことがあります。
一度は、下呂温泉の大浴場の露天風呂。さすがに牡丹雪が降りしきる中、男風呂の人影もまばらだったように記憶しています。そしてもう一回は、TVのロケでお邪魔した、奥飛騨温泉「朧」の個室に泊めていただいた夜中でした。
食事と酒宴を終え、雪が深々と降り積もる中、コテージ風の造りの自分の部屋へと戻り、このまま眠ってしまうのはもったいない!そうだこの部屋専用の露天風呂に浸りながら、熱燗でも煽って深々と降りしきる雪空を眺めよう!
さっそく酒に燗を付けて、盆にお銚子と猪口をのせ、降り積もった雪を踏みしめ、身を切るような寒さに身じろぎしながら、湯けむり漂う湯船へと慌てて浸ったものです。間接照明に浮かぶ雪空。真っ暗な闇から、大きな牡丹雪がひらひらと舞い落ちてくる様は圧巻!
ここが果たしてどこなのか、何時の時代なのか・・・。およそ日頃思いもしなかったような境地へ、誘われて往くようです。降りしきる雪は、俗世のあらゆる音と言う音や、諸々の雑念を覆い隠すかのように、ただただ静けさだけをもたらしてくれたものです。
どれほど雪の降りしきる夜に、露天風呂に浸りたいと思っても、こればっかりは天が定める事。前もって雪国の、露天風呂のある宿を予約しようが、必ずしもその晩に雪が降る保証はどこにもありません。
偶さか運が良いか悪いか、ただそれだけ。
でも出来うればもう一度、雪を眺めながら露天風呂に浸り、一杯きゅ~っと煽りたいものです。さすれば酒の味も、また一味も二味も、旨味が増すに違いなし!
そう言えば、3年ほど前に会津を訪ねた折。旅館の大浴場に檜風呂があり、そこに会津塗りの角樽と、同じく会津塗りの盃が置いてあり、「ご自由にお召し上がりください」と書かれてありました。何とも嬉しい心配り。湯船に浸りながら会津の銘酒に酔いしれた思い出があります。そんな粋な心配りに、益々会津が好きになったものです。
ここで「雪花火」の原曲、「夏花火」もお聴きいただきましょう。
こちらは、長良川国際会議場の大ホールでのLive版から、Jazz風のアレンジでお聴きください。
★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)
今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「乾布摩擦と押し競まんじゅう」。小学生の分団登校の集合場所だったどんぐり広場では、こんな冬ともなると、ご近所でも世話焼きとして有名な、元軍人だったと自慢するご隠居が、上半身素っ裸になって、使い古しの日本手拭いで乾布摩擦を始めたものです。そしてぼくら子供には、上半身裸になって乾布摩擦を指導してくれたものです。さすがに女子は免除されていたように記憶しますが・・・。果たしてどうであったか?女子は、集合時間を利用して、押し競まんじゅうをやって、寒さを凌いでいたようです。そして乾布摩擦が終わるや否や、押し競まんじゅうの輪の中へと飛び込んだものです。これまた、今じゃすっかり見る影も無くなり、遠い昭和の記憶の断片と化してしまったようです。
今回はそんな、『乾布摩擦と押し競まんじゅう』に関する、皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。