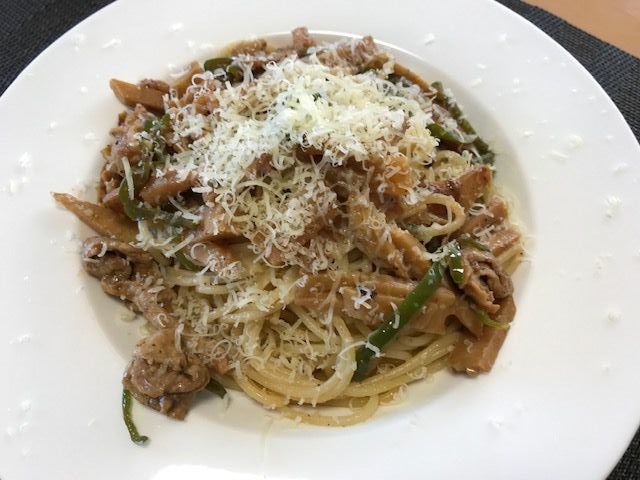今日の「天職人」は、三重県桑名市多度町の「和菓子職人」。(平成十六年十月九日毎日新聞掲載)
四季を彩る和菓子の華が 菓子器の中に咲き誇る 晴の日祝うお茶請けは 松竹梅に鶴と亀 両親の脇和服の君が ぼくの言葉に伏し目がち 「嫁に下さい」震う声 後は野となれ山となれ
三重県桑名市、多度大社の参道脇にある、和菓子の丸繁、七代目和菓子職人の蒔田(まいた)美喜代さんを訪ねた。

流鏑馬(やぶさめ)で賑う多度大社の参道脇。折からの雨が、多度の杜(もり)を洗い清めるようだ。雨乞いの神として知られる社に、木陰に宿る鳥の鳴き声がこだました。山門前を通り過ぎる、農具を積んだ軽トラック。山門に差し掛かると、運転手の農夫はハンドルを切りながら、頭(こうべ)を垂れて行き過ぎた。
「ここらに住んどる者らは、みな車で通りながらも、ああして頭下げてくんさ」。美喜代さんが店先から山門を見つめた。

もともと丸繁は、旧街道の宮川で江戸末期頃に創業され、五代目の時代に大社前へと移転した。代々当主の名には、「繁」の一字が受け継がれる。
しかし六代目は、男子に恵まれず、長女の美喜代さんが家業を継いだ。
短大を卒業すると、名古屋の和菓子屋で、当時女性としては珍しい製造部門へと、住み込みで勤務。男性中心であった菓子職人の世界に飛び込んだ。 「若かったから、怖いもん知らずやさ。あの人らの方が、気遣こてたんと違うやろか」。
幼い頃から両親の仕事振りを間近に見て育った分だけ、菓子作りの飲み込みは早い。和菓子細工に欠かせぬ、細い竹の箸も、使い勝手を良くするため、自らの手で削った。 「細工の飾りをキュッと摘んで、ヨイショッと載せるんやさ」。
四季折々の歳時記に応じ、縁起物から季節を愛でる品まで、甘味をまとった日本の四季が、一口大に仕上げられる。

一年半の住み込み修業を終え、多度へと帰省。両親と共に、参拝客相手の和菓子作りに精を出した。
二十四歳の年に銀行員の夫に嫁ぎ、桑名市内に新居を構えた。とは言え、実家の家業を放ってもおけず、通いで手伝いながら、妊娠・出産・子育てに追われた。 女和菓子職人は、妻として、母として、娘としての、四つの顔を使い分けながら、来る日も来る日も多度へと通い続けた。
「ある人に『毎日、子供ら連れて帰って来るんやったら、ここで暮らしたらええやんか』って、言われて。それもそやなあって」。三年前に、再び蒔田姓へと。

半世紀近く前、先代は雨乞いの神を讃え、最中「雨(あま)ごひ笠(がさ)」を発売。今尚、当時の製法を美喜代さんがしっかと受け継ぐ。
軒を伝う秋の長雨も、雨ごひ笠のご利益か。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。