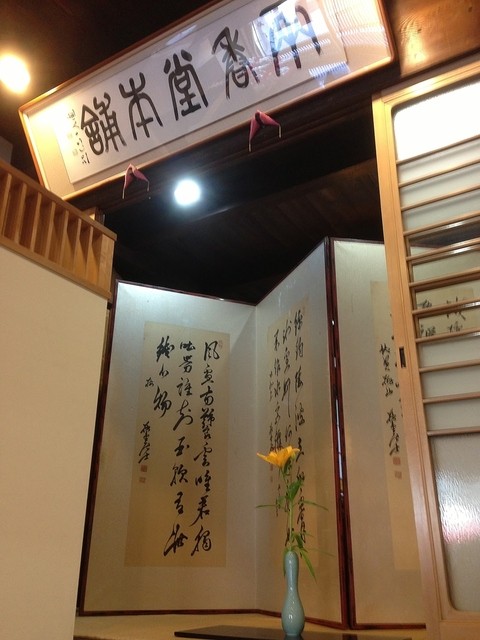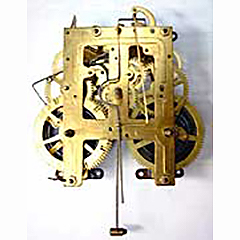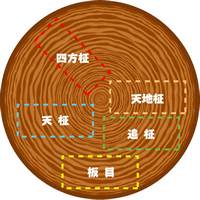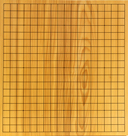今日の「天職人」は、岐阜県福岡町の「曲げわっば職人」。(平成十七年三月五日毎日新聞掲載)
卒業式の姉ちゃんは 袴姿で艶やかに お転婆娘何時の間に 頬にほのかな薄化粧 家族の宴祝い膳 蒸した赤飯待ちきれず 「摘み食いよ」と曲げわっぱ 蓋を開けたら玉手箱
岐阜県福岡町の丹羽木工所、二代目曲げわっぱ職人の丹羽昭二さんを訪ねた。

「柾目のわっぱは、もう出来んのやて」。 昭二さんは、早春の陽だまりの中で、山裾をぼんやり眺めた。
昭和三(1928)年、名古屋市中川区で誕生。しかし昭和二十(1945)年五月、一家は空襲で工場もろとも焼け出された。
総てを失い、母の在所を頼って福岡町へと移住。板壁の古い倉庫が仮住まい。天井からはお月様が見え、冬になると容赦なく雪が舞い込んだ。
「カボチャが盗まれたと言うと、直ぐに『あいつらや』と、余所者扱い」。その苦しさをバネに、掘っ立て小屋で工場を再興。景気の上潮に乗り、本格的に曲げわっぱ製造を開始した。
まず丸太を柾目になるよう、蜜柑割りに割く。昔の材は蝦夷松、今は東濃檜。次に蜜柑割りの材を立て、「く」の字の一遍と平行に二分(約六㎜)の薄さで、独特なわっぱ包丁を打ち込み、手槌で捻(ひね)るようにへぐ(剥ぐ)。

「へげる木かどうか、その見極めが肝心や」。六割は、へぎにくい外れ材。これらは折箱の材料として利用される。続いて腹当てをして、へいだ薄い平板の幅を合わせ、セン(鉋)で削る。「三年ヘボヘボ言うて、センで削れるようになるまで、楽に三年はかかったほどやて」。
次に三十分ほど釜で煮て、柔らかくなった材を縦長に置き、丸太の轆轤(ろくろ)を手足で押して板を巻き上げる。その後、型に組み込んで、天日で三~四日自然乾燥。底板に桟(さん)を取り付け、腰板を当て桜樺(さくらかば)で板を縫い上げ、曲げわっぱの蒸篭は完成する。

昭和三十三(1958)年に妻を得、二人の男子に恵まれた。「でも跡取りはもうおらん」。二人の倅は、医者に育て上げた。
「よう割れる木ほど、へぎやすい。トイゴ(木の性質)は一本ずつ違うんやで」。材木の仕入れは、目利が肝心。「博打はようせんけど、材木選びもそんなもんやて」。
やがて中国産の蒸篭が輸入され、柾目の曲げわっぱは衰退の一途。「もう柾目にへげる職人がおらんのやで、仕舞いやて」。昭二さんが寂しげに笑った。

たかが日用品。柾目で無くとも、赤飯やもち米は蒸せる。しかし職人は、曲げわっぱの胴に横たう、柾目という自然美に己の技を託す。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。