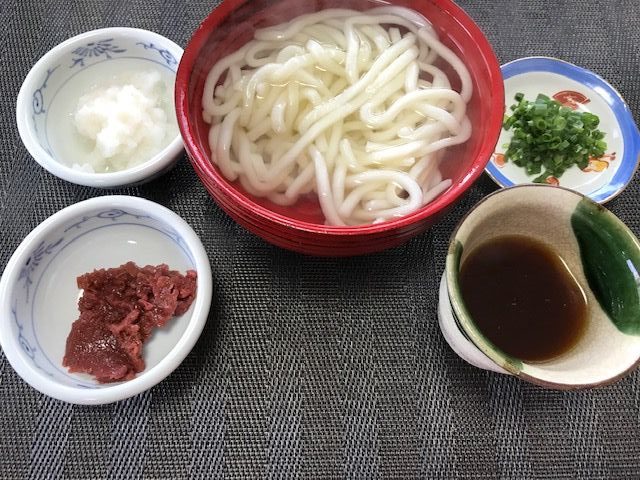思えば、去年も一昨年も、ホタルを目にすることがありませんでした。
そろそろホタルの恋の季節がやって来ているのでしょうか?
今日お聴きいただく「宵火垂る」は、深夜番組を始めて間もない頃に作った曲です。
その年にある小さな川沿いで、幻想的にホタルの乱舞する姿を目の当たりにすることが出来ました。
恐らくこれまで生きて来た中で、一番たくさんのホタルが見られた、実にファンタジックな夜のひとときでした。
出来うれば、観光化したホタルのスポットではなく、人気のない静かな場所で、藪蚊に喰われるのを覚悟で、ぼ~っといつまでも眺めたいものです。
以前、とある温泉に泊ったところ、近場のホタルスポットへマイクロバスで案内いただける機会がありました。
浴衣姿で下駄を鳴らして、人気のない細い車道を歩いてすすむと、何と群れからはぐれたのか、1匹だけ迷ったかのようにフラフラと舞うホタルを見ることがやっと出来たものです。
案内くださった旅館の方は、1匹だけでもホタルが舞ってくれてほっとされたように安堵されていたのが、とても印象に残っています。
ところがところが!
夕餉の折にしたたかにお酒を飲んだからか、前をはだけてしまう浴衣のせいか、もう体中藪蚊に刺されっぱなし!
急いで売店で虫刺されの薬を買ったものでした!
藪蚊は酒の匂いに寄って来るって、やっぱり本当のようですね。
それよりも感心したのは、土産物の並ぶ旅館の売店のレジ前に、虫刺され用の塗り薬が、大きなPOPの前にデーンと並んでいたのは、ホタル観賞のぼくのような酔っ払いたちが慌てて買い求めるからなんでしょうねぇ。
また今年ホタルがご覧になられた方は、教えてくださいね!
そんなわけで今夜の弾き語りは「宵火垂る」をお聴きください。
「宵火垂る」
詩・曲・唄/オカダ ミノル
君のうなじに 淡い灯りが そっと舞い降りた 宵火垂る
清か瀬音に 君のため息 肩に回した 手を握る
わずかな命ゆえに 愛おしい 淡い灯りを賭け 燃え尽きる
宵火垂るよ 今宵一夜 二人の行く末 そっと照らせ
君をどれほど 愛してるか どんな言葉でも 言い尽くせぬ
淡 い 月 影 君の横顔 見詰めるぼくを 振り返る
わずかな命だから 心のまま 君を思いの丈 愛し抜こう
宵火垂るよ 今宵一夜 愛し合う二人を そっと灯せ
二人の夏の初め 彩って 儚く燃え尽きようと 忘れない
宵火垂るに 想い重ね 君との愛を 永遠までも
★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)
今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「初めて手にした自動車運転免許証の思い出!」。なんでも明後日25日は、「指定自動車教習所の日」なんだとか!1960年、つまり昭和35年の6月25日に道交法改正法が施行され、公安委員会が指定した自動車教習所を卒業すれば、技能試験が免除される制度が誕生したそうです。ぼくの子どもの頃の記憶や、映画Always 三丁目の夕日で見ると、まだまだ昭和39年の東京オリンピックの時代ですら、交通量が少なかったわけですから、この法律はやがて訪れるモータリゼーションに先んじて誕生した、いわば画期的な法律だったのかも知れませんね。
家の父は車の免許を持っていなかったため、わが家ではぼくが車に乗るまで、車はありませんでしたねぇ。ですからどこに行くのもバスや電車の交通機関ばかり。でもやっと車が持てるようになり、通勤する父を助手席に乗せ、ぼくも毎朝バイトに出掛けていた頃は、父も嬉しそうにして、時折なけなしの小遣いから、千円札をぼくのポケットにねじ込んでくれたものでした。今思えば、仕事帰りに飲みに行くわけでもなく、会社と家を行き来するだけの父は、わずかばかりのなけなしの小遣いで、大好きな煙草を買うお金さえ節約して、ぼくにそんな送迎代金をくれたのやも知れません。ありがとう!お父ちゃん!
今回はそんな、『初めて手にした自動車運転免許証の思い出!』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。