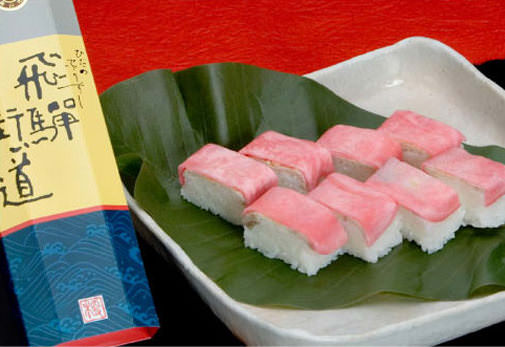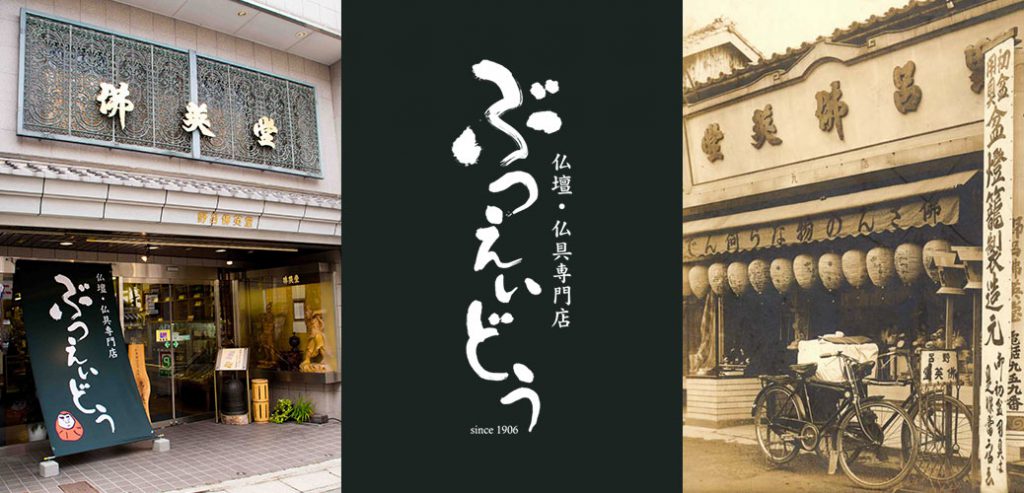今日の「天職人」は、岐阜県高山市の「椅子革裁断師」。(平成21年10月28日毎日新聞掲載)
蜜柑の箱に将棋板 古く傾(かた)いだ椅子二脚 祖父と隣りのご隠居は 舟漕ぎながら駒を指す 「さぞかし尻も痛かろう」 父はボロ屋で裏革を がめて座面を包(くる)み込み 「これでええ夢見れるやろ」
岐阜県高山市で、北欧家具を製造するキタニ。椅子革裁断師の植田一良さんを訪ねた。

「ある日、お婆さんがみえて、『爺さんが昔、職人に作らせた椅子を、直してもらえんか。孫に使わせたいで』と。座面を開くと、中に緩衝材として藁と草が。だからそのまま、新しい藁と草を詰めて再生したんやさ。そしたら大喜びで。職人冥利に尽きるってやつかな?たかが椅子1脚、でも生き物なんやさ。職人が魂込めて、命を吹き込めば、末永く生きるんやで」。一良さんは、懐かしげに笑った。
キタニでは、飛騨匠の末裔たる家具職人たちが、己が手力を頼りにその技を競い合う。
一良さんは昭和36(1961)年に誕生。
だが小学2年の年、両親が離縁した。
「勉強より、物作りや機械いじりが好きで、自動車の整備士になろうと」。
工業高校を出ると、お茶、火薬、包装資材等、幅広く手掛ける鍋島商店に入社。
「梱包機の修理担当で入社したはずが、1月毎に全部の事業部門を回らされて」。
入社からわずか3ヶ月を迎えた時だった。
「お前、行って来いって」。
子会社であるキタニのウレタン加工所へ異動。
大阪から来ていた職人が、怪我をし欠員が出たからだ。
「巨大な食パンみたいな、幅2㍍、奥行き1㍍、高さ80㌢ものウレタンの塊を、スライス機で薄く梳(す)いて。椅子のクッションに加工し、家具メーカーに納めるんやさ。ここらは脚物(あしもの)の産地やで」。
次第にウレタン加工から、布張り仕上げへと業務領域も拡大。
いつしか木工職人も増え、自社製品の製造へ。
「ちょうど15年前。これからは福祉やと、社長が福祉の先進国である北欧へ視察に。すると倉庫の片隅に、昔の北欧家具が。それをコンテナで持ち帰って来たんですわ。椅子も何10脚と。最初皆も呆気にとられ、『社長が北欧からゴミ買い込んで来たぞ』って。でもよく見ると斬新な作りで。バラした途端、職人魂に火が点いて、もう夢中。ソファーも座面をはぐると、草や獣毛が出てくるし」。

職人たちは獲り憑かれた様に、半世紀前の北欧家具職人たちの手業を学んだ。

そして平成8年、北欧家具の復刻製造へと乗り出した。

裁断師の作業は、3次元に描かれた図面から、2次元に座面の型を起こし、革を裁断することに尽きる。

「それが縫い合わされて3次元に仕上がると、ゾクゾクッとして。牛革の腹と背は伸びるが、尻は伸びんから、それを計算に入れんと」。
平成16年、同じ職場のかづみさんと、7年越しの恋を実らせ婿入り。
やがて二女を授かった。
「20歳のころ、尻まくって辞めようかと。でも年配の女性が早まるなって引き止めてくれて。でも辞めんでよかった。裁断師として、型出しする面白さにも気付かんかったやろし、妻とも巡り逢えず仕舞いやったろで」 。
きっと誰もがいつかは巡り合う、一人に一つの天職一芸。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。