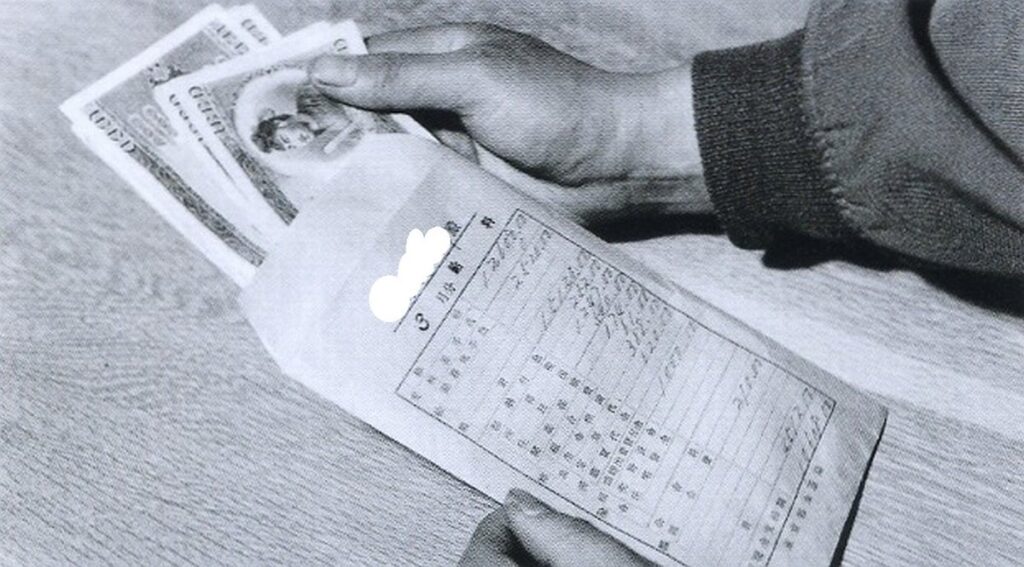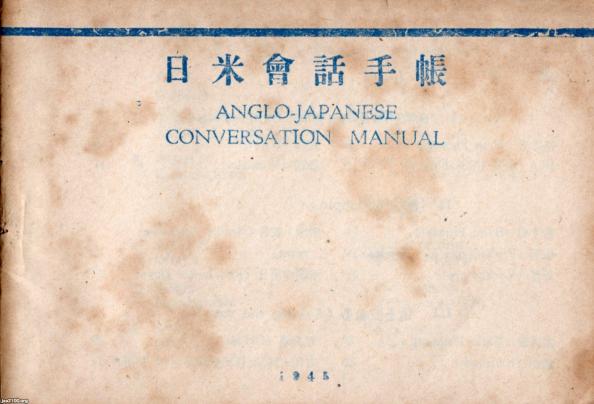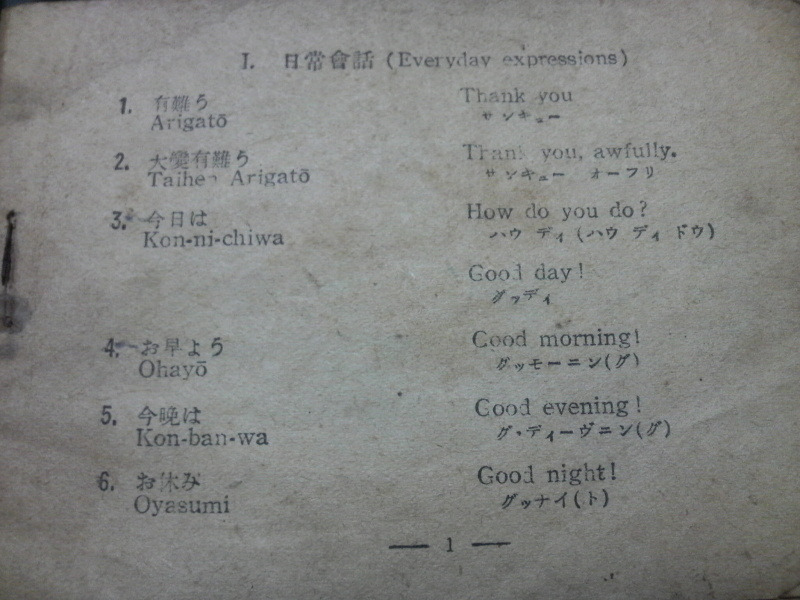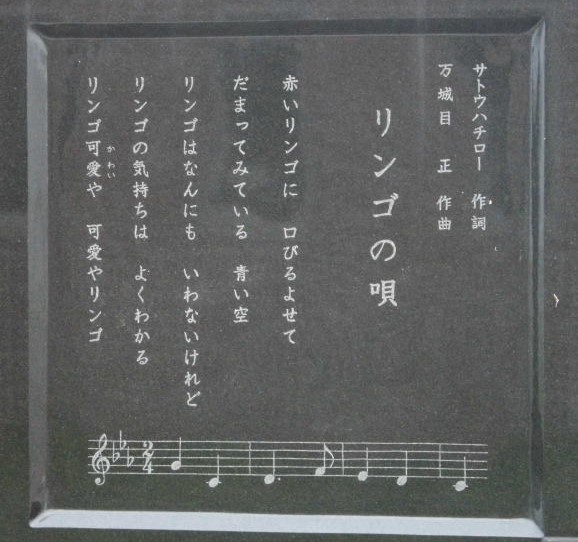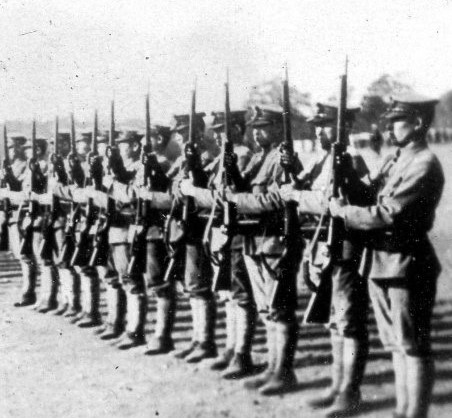「お宅のご主人、いつも背広をピシーッと着こなして。颯爽と自転車でご出勤やけど、お勤めは一流会社?」。
「そんな…」。
物干し竿から、洗濯物を取り入れる母の声がした。

「ごく平凡やよ」。
そう言うと、父の青色の作業着を、慌てて丸め込んだ。

父は昭和半ばの高度成長期を、鉄工所の溶接工として勤め上げた。
毎朝数少ない背広に袖を通し、数本のネクタイをとっかえひっかえ結んで。
ロッド式ブレーキの、頑丈な自転車に跨り、昭和後半の時代を駆け抜けた。

ある日のこと。
「働くお父さん」という作文の宿題で、母に伴われ父の職場へ。
すると油塗れで真っ黒な、菜っ葉服姿の父が現れた。
「背広姿しか見た事ないで、ビックリしたやろ?」と父。
油汚れで真っ黒な軍手を取り、額の汗を拭い煙草に火を付けた。

「鉄と鉄をくっつけるんが、お父ちゃんの仕事や」。
夕陽に浮かんだ、油塗れの父の笑顔。
汗と油と煙草臭さが、昭和の繁栄を築いた、男たちの匂いだった。
「背広より、ずっと男らしいわ」。
ぼくがそう言うと、父はロイド眼鏡を持ち上げ、油塗れの指先で目頭を押さえた。

母はあの日以来、通りに面した一等地に、薄汚れた菜っ葉服を、堂々と翻すようになった。
一方、父は「3着の上下変えたら、9日も持つで」と。
ついに定年のその日まで、古びた3着きりの背広姿で押し通した。
「モッチャンは、貧しかったあの頃も、洒落者やったな」。
父の遺影を眺めながら、叔父のつぶやいた言葉に、遠い日の記憶が鮮やかに甦った。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。