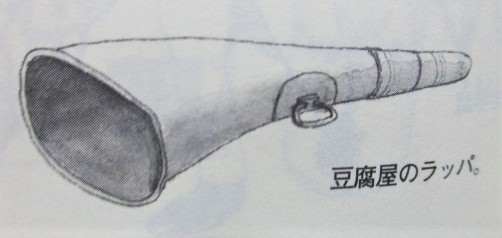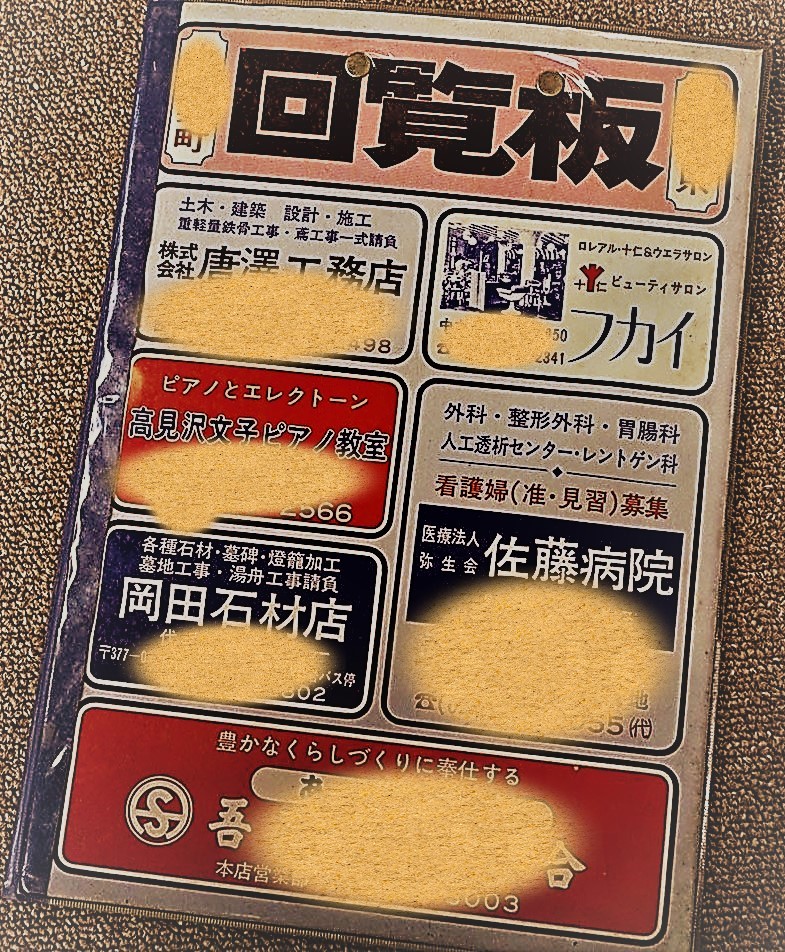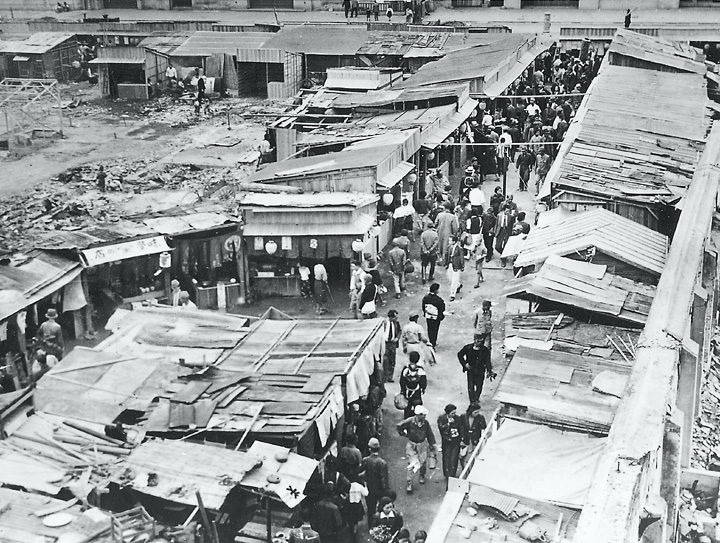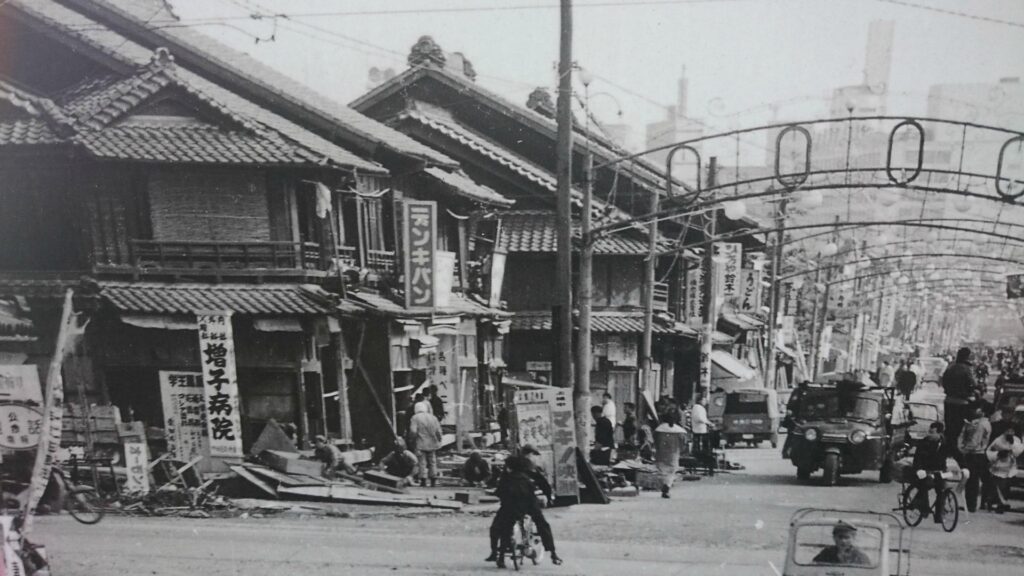「カズ君の誕生祝いに、よう来てくれたなぁ。たぁ~んと食べてや!」。
中学1年のある日。
同級生のカズ君のお母さんが、見たことも無いすき焼き用の大きな牛肉を、手際よく炒め煮始めた。

わが家のすき焼きと言ったら、脂身が勝る細切れ肉がやっと。
正直、羨ましくてならなかった。
そして恐る恐る、お肉を口へと運ぶ。
すぐさま、言いようのない後ろめたさに苛まれた。
ぼくだけこんな上等な肉にあり付けたことを、両親に何と詫びれば善いものかと。
次におばちゃんは、これまで目にした事も無い、表面がギザギサしていて、拍子切りになった食材を、まるでお肉の様に炒め煮始めた。

「この子、お肉が嫌いなんやて。好物はこのカクフやわ」と、おばちゃん。
カズ君が旨そうに食べるカクフを眺めていると、それがどうにも気になる。
まるでぼくの心を見透かしたかのように、カズ君が「これも食べていいよ!」と。
お言葉に甘え、さっそく口へと運ぶ。
そっと目を瞑り噛み締める。
すると確かに、お肉の様な食感ではないか!
しかも程よくすき焼きの味が染み、得も言われぬ味がした。
あまりの美味しさに惹かれ、高級な牛肉には目もくれず、カクフばかりを奪い合ったほど。
母は鹿児島、父は三重の出。
故に尾張と美濃地方に根付いた、角麩の食文化には無縁で、一度も食卓に上ったためしも無かった。
わが家に戻り母に話すと、「へぇー、あの角麩って、そうやって使ったらええのか?あれやったら値打ちやで、いつでも買うて来たるわ」と。
しかしそれが仇に!
それで無くとも、僅かしか無かった細切れ肉の量が減らされ、牛肉とは比べ物にならぬ安さの角麩が、代用品として堂々と罷り通ることに。
それがきっかけで、美濃と尾張に根付いた麩の恵みを知った。

清流長良の恩恵に与る、水都大垣の井戸水。

通年14~15℃の地下水に晒された、麩屋惣の生麩の肌触りは、まさしく天下一。

美濃と尾張に麩屋は数あれど。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。