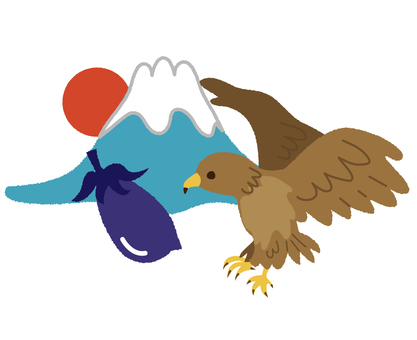某局のTV番組で、わずかな期間の放送でしたが、「夫婦善哉 金婚庵」という、番組がございました。
ぼくとラジオパーソナリティーの森下リカちゃんが夫婦役で、毎回金婚式をお迎えになられたご夫婦や、間もなくお迎えになるご夫婦をお招きし、夫婦道について新婚間もないぼくとリカちゃんが教えを乞うと言うものでした。
しかしながらこの番組は、玉虫色にコロコロと変るお偉いさんのご意向で、わずかワンクールたらずで、あっという間に終わりを迎えることとなったのです。
さてこのLiveのバックに移っている写真は、その「夫婦善哉 金婚庵」の番宣のため、大雪に見舞われる中、テーマソングとなった「ふたりの長良川」の歌詞に合わせる形で、現地ロケを行った時の、長良川鉄道北濃駅でのシーンです。
まずは、ミノルとリカの「ふたりの長良川」からお聴きください。
「ふたりの長良川」
詩・曲・唄/オカダ ミノル 唄/森下リカ
雪に埋もれた高鷲(たかす) 夫婦滝で誓った
ふたり寄り添い生きてゆこうと 舞い上がる白鳥(しろとり)に託した
夜を明かして踊れば 八幡の城下町
このまま何処までも あなたとなら
喜びと哀しみ 幸せと不幸せ
ふたり手をとり美濃路を下る 長良の鮎がその身を任(まか)すように
長良橋 金華橋 互いをただ信じて
この命果てるまで あなたと伴に
ふたり生きた証しが この川を遡る
あとは海へ還ろう 流れるままに
ふたり生きた証しが この川を遡る
あとは海へ還ろう 流れるままに
この「ふたりの長良川」を深夜のラジオ番組で、毎週流していた頃、老夫婦の奥様からお手紙をいただきました。
「この歌にあるご夫婦のように、私共夫婦も喜びも哀しみも二人で分かち合い、長良川を下りながら生きて行こうと思います」と。
なんだかとっても嬉しいお便りだったと、記憶しています。
続いては、ぼくの弾き語りの「ふたりの長良川」をお聴きください。
長良川沿いの町には、それぞれの文化と歴史がてんこ盛りです。郡上と一口で言っても、高須と白鳥も、そして大和にしても八幡も、似ているようでも非なる部分も多く見られるものです。今のように何処へでも、車でひとっ走りと言う時代ならともかく、自分の足だけが頼りの時代であれば、集落の周辺から抜け出すこともままならず、ましてや山間の集落ならなおさらの事。だからこそ似て非なる独自の文化や風習が、集落の中で脈々と息づいていったのでしょう。長良川沿いの町で、色んな方々からお話を伺うと、言葉の端々にも若干の違いまで感じられるものです。
清流長良川が育んだ、美しい文化や風俗。いつまでもいつまでも、受け継がれてゆくことを願って止みません。
続いては、ボサノババージョンの「ふたりの長良川」、そして長良川国際会議場大ホールでのLive音源からの「ふたりの長良川」と、2曲お聴きいただければ幸いです。
まずは、スタジオ録音版からです。
そして長良川国際会議場大ホールのLive版です。
★実は先週の12月31日の深夜ブログで、翌日の1月1日にお誕生日をお迎えになる「トトロんぽいけどとんとろとんとんとん」さんの、お祝いソングを唄わせていただくお約束をしておりました。しかしぼっくがうっかり失念。録音する事を忘れてしまっておりました。それに気が付いて、さっそくメールでお詫びし、1週間遅れでのお祝いでご了見いただきました。そしてもうお一方、明日1月8日にお誕生日をお迎えになる、「黄色いモンブラン」さんのお祝いを、今夜はご一緒にさせていただきます。それでは「Happy Birthday~君が生まれた夜は」を、今夜も唄わせていただき、ささやかなお祝いとさせていただこうと思います。
★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)
今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「鏡開き」。昔は真空パックの鏡餅なんて、洒落たものなんてありませんでしたから、1月11日の鏡開きの日にゃあもう、鏡餅なんて黴まるけ!お母ちゃんが鏡餅を水に浸し、菜切り庖丁のアゴのところで、黴をこそぎ落としていたのを思い出します。これは家のお母ちゃんだけかも知れませんが、小さな鏡餅を家中のあちらこちらに飾り付けておりました。ですから便所にも当然小さな鏡餅と、小さな豆注連縄が飾られていて、鏡開きの日には便所にお供えした小さな鏡餅も、他の物と一緒にお母ちゃんが黴を取り、そのまま火鉢の上でコトコトと煮立っているぜんざいの中へ!ですから、便所にあった鏡餅がもうどれかさえ分からず、「ええい!ままよ」っとばかりに、知らぬ存ぜぬを決め込んで美味しくいただいたもの物です。さすがに今となっては、トイレで鏡餅を見掛けることはありませんねぇ。皆さんのお宅ではいかがでしたか?家のお母ちゃんだけだったのかしらん?
今回はそんな、『鏡開き』に関する、皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。