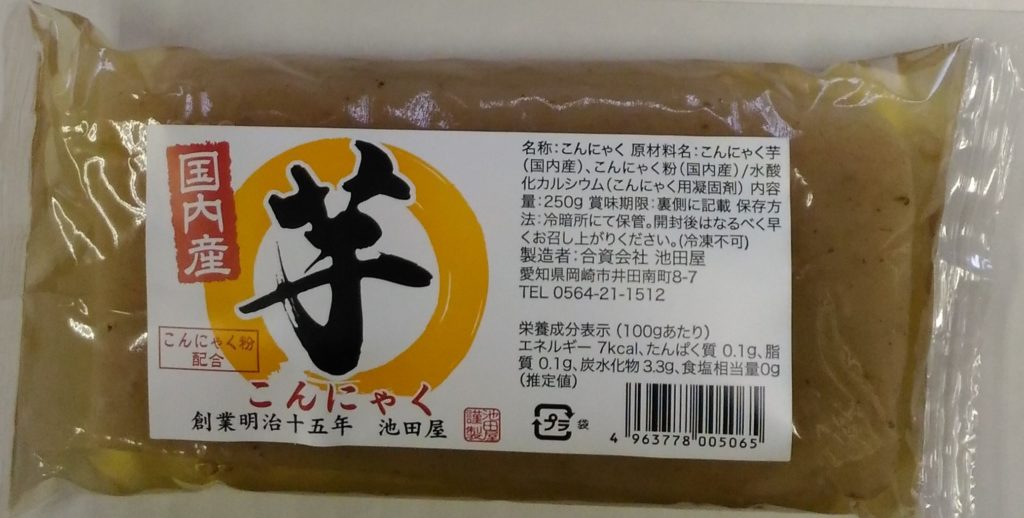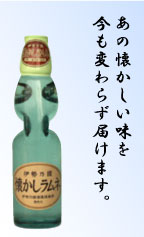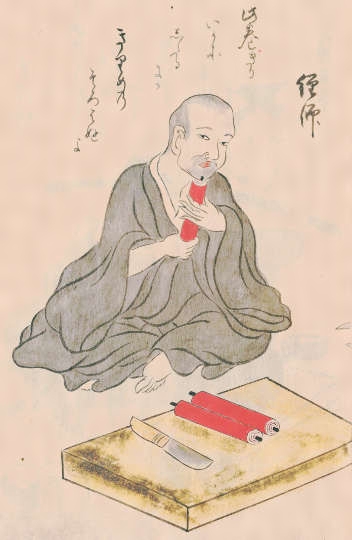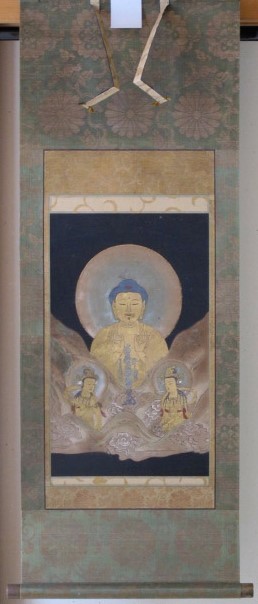唐突ですが、ぼくは朝が好きです。昼間よりも夜よりも。
しかも海辺とか山裾の高原などで迎える、誰にも穢されていないような、無垢な朝がとても好きです。
朝焼けに染まった東の空を眺めていると、何だかとっても素敵な事が起きるような気がして、ついついワクワクして心が弾んでしまいます。
人にはそれぞれで、朝型の方も見えれば、夜型の方だってお見えになります。これをお読みの貴方は、どちらでしょうか?
ぼくはどちらかと言えば、朝型の部類に属すると思います。子供の頃から今でも、朝早いのは一向に苦になりませんが、夜っぴて原稿を書いたり、曲を作ったりといった事は、まずもって出来ません。
それよりも心地よく酒を愉しむと、後は勝手に睡魔が手招きをしてくれますから、もうベッドに潜り込んで高鼾です。「まっ、後は明日やればいいや」ってなもんで。
ところが朝はどんなに早くても、ピシッと起きれちゃうから不思議です。朝が弱い方には、申し訳ない限りですが・・・。
今日お聴きいただく「君だけにMorning」は、やはりぼくがまだ22~3歳の頃の作品だったと記憶しています。この曲もセンチのアレンジによる作品と、ヤマハのスタジオミュージシャンによるアレンジ作品3種類があり、それぞれにお聴きいただければ幸です。
まずはぼくの拙いギターの弾き語りで「君だけにMorning」をお聴きください。
「君だけにMorning 」
詩・曲・唄/オカダ ミノル
君だけにMorning 目覚めた朝に弾ける あどけない笑顔に 口付けを贈るよ
君だけにMorning やわらかい陽射しを 独り占めして君は 輝いている
ざわめく街を抜け出して 二人で夜を駆け抜ける
海沿いをただひたすらに 朝焼けが見たいから
君への愛を語るには 波打つ調べ聞きながら
朝焼けのライトを浴びて 砂浜のステージで
君だけにMorning 目覚めた朝に弾ける あどけない笑顔に 口付けを贈るよ
君だけにMorning やわらかい陽射しを 独り占めして君は 輝いている
透き通る風を感じて 裸足で駆け出す君の
セピア色に輝く肌 眩しいほど素敵だよ
君だけにMorning 目覚めた朝に弾ける あどけない笑顔に 口付けを贈るよ
君だけにMorning やわらかい陽射しを 独り占めして君は 輝いている
セピア色に輝く肌 眩しいほど素敵だよ
君だけにMorning Good Morning I Love You
君だけにMorning Good Morning I Love You
若い頃は朝陽を無限大に感じられていたのに、「あとどれだけ朝陽を、拝めるだろうとそんな数を数えるような人生も晩年。だからこそ、毎日毎日当たり前のように昇ってくれる朝陽を、それがあたかも当たり前のことなどとは決して思わず、感謝の心で拝めるようになって来ていることに、はたと気付いております。
続いては、深夜放送でもお聴きいただいておりました、ヤマハのスタジオミュージシャン版のアレンジによる「君だけにMorning」をお聴きいただきましょう。
そして薄れゆく記憶を手繰り寄せつつ、古びたカセットテープから、センチメンタル・シティー・ロマンス版のLive音源の「君だけにMorning」を発見しました。
こちらもぜひ、お聴き比べください。
そして何と何と、ヤマハのスタジオミュージシャンとデモ・レコーディングする前の、パイロット版のような別のアレンジの「君だけにMorning」も古びたカセットにありましたので、こちらもお聴き比べいただけたらと思います。
アレンジ一つで、同じ曲であっても、随分雰囲気が変わるものです。懐かしい限りです。
★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)
今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「野イチゴ?蛇イチゴ?」。ぼくの小学生の頃の通学路は、田んぼの畦道のような、舗装もされていない凸凹道の細い農道でした。だからこの頃になると、農道の両脇にもレンゲ草にタンポポ、シロツメクサなどが芽吹き、春の景色を彩ってくれたものです。レンゲは花びらを取って蜜を吸ったり、女の子たちはシロツメクサの花冠作りに夢中だったり。そんな中、毎年腕白坊主どもの間で話題になったのが、「野イチゴって蛇イチゴ?」「食べられるんだろうか?」と。さすがに小心者のぼくは、「蛇イチゴ」って名前に怖気づいて、食べたことはありませんでした。でも調べて見ると、とても美味しいものでは無いものの、食べられなくは無いそうですねぇ。それに「蛇イチゴ」と言う名からして、毒でもありそうな気がしますが、これまた全く無毒だとか。「蛇イチゴ」の由来は、どうやら湿った草地や畦道など、如何にもヘビが出て来そうな場所に生えるからとか、蛇イチゴを食べにくる小動物を、蛇が狙いにやって来るから、などとも言われているようですねぇ。皆様は、って女子にはそんなご経験はきっと無い事でしょうが、年季の入ったかつての腕白坊主の方は、召し上がったことがあるやも?
今回はそんな、『野イチゴ?蛇イチゴ?』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。