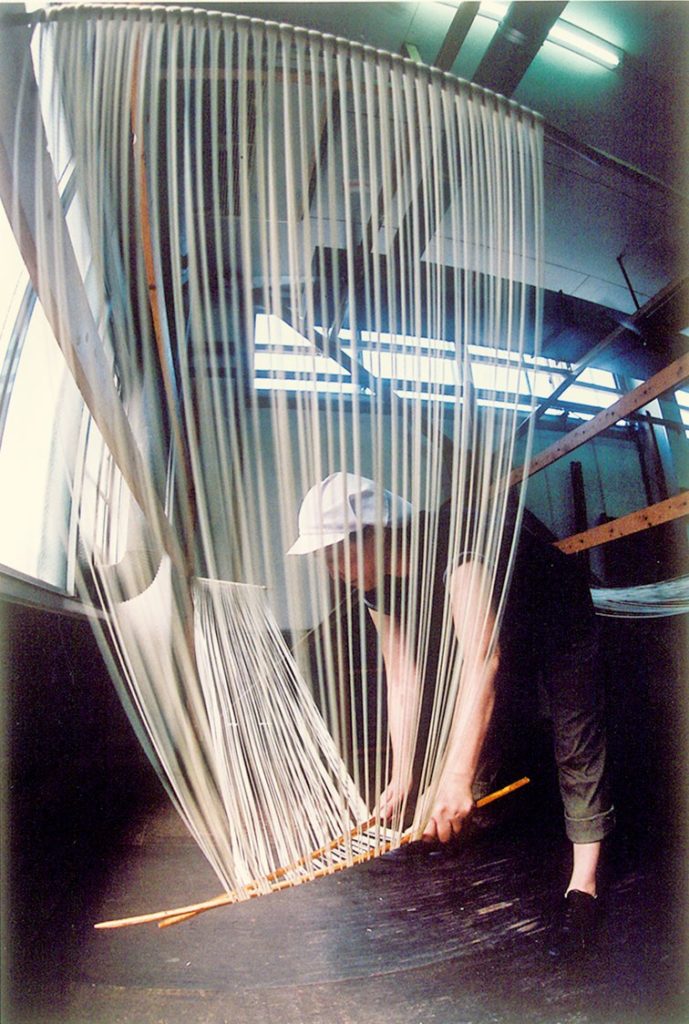写真は参考
写真は参考
ぼくが小学校の低学年の頃は、近所回しにたくさん子供たちがいたものです。
特に家のお隣やらご近所には、なぜか同じ年の女子がたくさんいて、藁縄一本を輪っかにして電車ごっこや、花いちもんめやゴム跳びにと、それでなくとも少ない男坊主どもは、引っ張りだこの遊び相手でした。
中でも最もぼくが苦手としていたのは、「ママゴト遊び」。
そのお相手となるのは、最もご近所に住んでいた、お隣の「フミちゃん」、その3軒向こうの「タカちゃん」、それに「マアちゃん」が、それぞれに自慢のママゴトを玄関先で広げて、ぼくを待ってるんです。
今となって思えば、その小学校低学年の頃が、ぼくの人生の中で最もモテた時期だったようです。
しかし当時は、なんせ酸いも辛いも噛分けられるほどの人生経験なんてありませんから、3人の女子たちのなすがまま!
やっぱり男坊主どもよりも女子は、そんなに小さな頃であってもおませなものですねぇ。
どこで覚えたんだか、ママゴト遊びのシナリオがそれぞれにちゃんと描かれていて、ぼくの役柄と台詞まで指定されるのですから、たかがママゴトと侮っちゃあいけません。
きっと3人それぞれに、お母さんとお父さんの会話をそっくり真似たものなのでしょうが、ぼくは順繰りに3人のママゴト屋敷に「ただいま!」と、会社から帰って来た夫を演じさせられるのですから、とても人も羨むハーレム状態というわけじゃあありません。
だいたい3人のシナリオには共通点がありました。それはママゴト遊びの道具が、「ママゴト(飯事)」というくらいですから、炊事道具のフライパンや鍋に、プラスチックのオムレツやらハンバーグにウィンナーといったものが大半。よって旦那役のぼくが会社から「ただいま」と帰ってくるところから始まるという筋書き。すると女房役の女子が「あら、あなたお帰りなさい!お風呂になさいますか?それともご飯になさいますか?」と歯の浮くような台詞を並べ立てるという設定。でもそこで間違っても、「じゃあ、ひとっ風呂浴びてくるか!」なぁ~んて宣うものならさあ大変!
だってママゴト遊びには、キッチンとダイニングはあっても、お風呂はあくまで物の例えとして、飾り物のように添えられた言葉でしかありませんし、お風呂場の設定などどこにもないわけですもの。
「じゃあご飯をいただくとするか」とかなんとか言わされて、手垢塗れの汚れが付いたオムレツなんぞを、さも旨そうに食べるふりをせねばならないのですから、たまったもんじゃあありません。
皆様もそんなママゴト遊びのご経験、きっとおありになったのでは?
今夜は、ちょっとメルヘンチックな「まあちゃんのママゴト」を、弾き語りでお聴きください。
昨今の新型コロナの感染予防で「Stay Home!」がスローガンのように聞こえてまいりますが、大切な命を守るため、一人一人が出来るのは、やっぱり「うつらない」「うつさない」ことですよね。
そんなぼくのStay Homeは、もっぱら趣味でもある「残り物クッキング」で、大人のママゴトに精を出しております。
それでは幼い頃を思い出していただきながら、「まあちゃんのママゴト」お聴きください。
「まあちゃんのママゴト」
詩・曲・歌/オカダ ミノル
垣根に背伸びぼくを呼ぶのは ドングリ眼のまあちゃん
ラジオ体操に遅れるわと おませな口ぶりを真似た
お昼寝の後は決まって 自慢のママゴト広げて
プラスチチックのオムレツ差し出し 「さあ、召し上がれあなた」
今夜は娘も夢の中さ たまにゃ二人でどうだい
当たり目安酒酌み交わせば 娘が起き出し「私も」
起き抜けの後は決まって 自慢のママゴト広げて
塩化ビニールの海老フライを 「さあ、召し上がれあなた」
ねぇまあちゃんやっぱり 遺伝子は侮れないね
小さな君と瓜二つの おませな横顔愛しい
この「まあちゃんのママゴト」も、どうでしょう、今から約40年近く前の作品だったと記憶しています。
近所の同じ年の女子の、「フミちゃん」「タカちゃん」「マアちゃん」の3人の中で、なぜ「まあちゃんのママゴト」になったかと言うと、それほど深い意味合いがあったわけではありません。
単に、「フミちゃん」「タカちゃん」よりも、「まあちゃん」の方が、メロディーに載せやすく、座りがよかったからです。
★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)
今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「ザリガニ釣り!」。なんでも今日5月12日は、「ザリガニの日」なんだとか。昭和2(1927)年に、食用蛙の餌としてアメリカザリガニが20匹持ち込まれたそうです。ところがそれが逃げ出し、あっという間に日本国中で繁殖したのだとか。ぼくが小学校の低学年の頃、昭和40年頃にはわが家の周りの田んぼの用水路とかに、アメリカザリガニがウジャウジャといたものです。ぼくはそこらへんで拾った棒っ切れにタコ糸を結わい付け、学校給食で出た魚肉ソーセージの残りを、糸の先に結び付けてアメリカザリガニの目の前へと放ってやったものでした。すると大きなハサミで器用に魚肉ソーセージを掴むので、それっ今だってな感じで釣り上げたものです。魚肉ソーセージの餌が無くなると、釣り上げたアメリカザリガニを一匹犠牲にして、殻を剥いた尻尾を餌にしたものです。
今回はそんな、『ザリガニ釣り!』。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。