今日の「天職人」は、愛知県岡崎市の「石版刷師」。(平成20年3月11日毎日新聞掲載)
今日の煮物はさつま芋 何だか嫌な予感した 父は箸止め芋睨み 「誰やオバQ彫ったんわ」 図工で習(なろ)た芋版画 復習しよと見渡せば 輪切りの芋がまな板に 彫刻等で腕試し
愛知県岡崎市、石版刷師(すりし)の深見充彦さんを訪ねた。

「毎日仕事で一歩も外出んと、籠の鳥の状態ですわ」。充彦さんは、伏し目がちにこっそり笑った。
充彦さんは昭和33(1958)年、農家の長男として誕生。
大学院では美術を専攻した。
「普通なら美術の教師だったんですがねぇ」。
在学中、仏具の蒔絵を研究する同級生の女性に紹介され、碧南市の石板画作家を訪ねた。
「リトグラフの技法に興味がわいて、どんなものかと通い始めたんです。そこにはどうしたわけか、自然と詩人や作家、それに絵描きなんかが集まって来て。彼らとの人の輪が何より楽しくて。大学行かんと碧南通っとったくらいですわ」。
大学院を修了すると、長野県坂城町の刷師の下へと修業に入った。
昭和59(1984)年、同級生で蒔絵の研究を志していた由美子さんと結婚し、長野で新婚生活へ。
昭和61(1986)年、4年の修業を終え、長女の誕生を間近に控え岡崎の実家へと引き揚げた。
「最初は14畳ほどの農機具小屋にプレス機一台置いてのスタートでした。それも印刷屋のお下がりの石版刷機で」。

今は立派に立て替えられた工房の一角を、懐かしそうに眺めながらそうつぶやいた。
だが所詮、無名の刷師。
仕事が勝手に舞い込むはずはない。
「仲間が回してくれるわずか数万円の仕事がやっと。不得手な営業しに名古屋の画廊を回ったもんだって。でも信用も実績も無いから、作品を見せろって言われるのがオチ」。
そんな努力が報われるような、大口の仕事が3ヵ月後に飛び込んで来た。
「150万円の大仕事でした。あんまりにも力入れすぎて、完成までに半年も掛かって。その分何回もやり直して、材料費も馬鹿にならず結局赤字でしたけど」。

充彦さんは創業時を懐かしそうに振り返った。
翌昭和62(1987)年、夫婦は乳飲み子の長女を伴い渡米。
ニューメキシコ州のタマリンド・インスティチュート(石版画研究所)で、本格的な石版を学び己に自信を付けようと。
「『英語なんてしゃべれんでも、技術に言葉はいらん!』って強がって。親との同居も嫌だったし、それほど大変だなんて思わんと。若かったから、もう『矢でも鉄砲でも持って来い』って感じで」。
刷師の仕事はまず、原画に透明のフィルムを当てトレースし、輪郭線を石灰石や大理石の原版に写し取る作業に始まる。
次に描画材で輪郭線の内側に描画を施す。
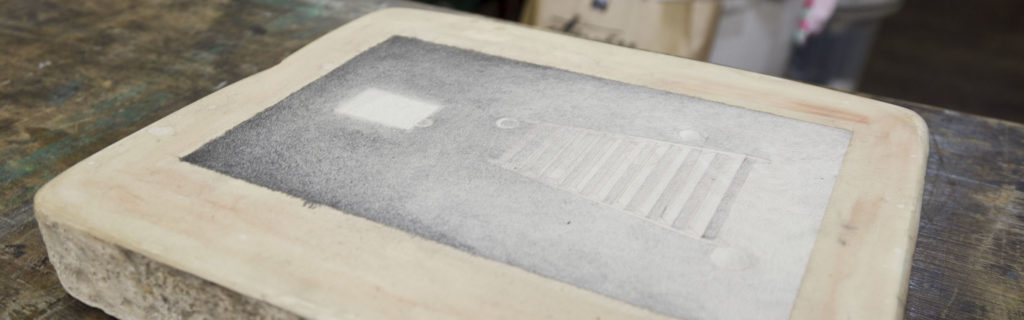
この原版作りは、原画の色の数だけ繰り返される。
通常でも30~40版は必要だ。
その後ハンドローラーに原画と違わぬ色を載せ、原版に刷り合わせプレス機にかける。
今やコンピューターで色分解の時代。
「でもやっぱり微妙な色の濃淡は、作家の癖を読み取って職人の勘で表現せんと」。
微妙と絶妙の差は、職人の色加減一つに委ねられる。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。


キャーッ!!
私の人生、微妙だわぁ。何が足らんかった?
ええっ、何か不足しているものがありましたかぁ???
今や、コンピューターの時代
段々!
人間の手から離れてゆくんでしようかねぇ?
近い将来、車も自動運転になる・・
そんな日がくるとは・・
オカダさんの「ほろ酔いライブ」だけは
人間らしく気取らず、ホッと一息癒される
ライブであって欲しいもんです。
確かにそうですよねぇ。
じゃあぼくも、コロナ制圧後に、気取らず力まずほのぼのとしたLiveを開きたいと思います!
今晩は。
石版堀師のお話ですね。石版堀師さんが見えたのですね。
私は、知りませんでした。 ブログで、勉強になりました。
石版堀は、手作業なのですね。
石版刷り 初耳だったから調べてみたけど 難しくてよくわからなかったです。
どうして石版なんだろう?
どんな歴史のもと 石版になったのか?
etc…
昔からの作品を見てみると これまた千差万別でますます難しくなっちゃいました(笑)
けど ただ々単純に 素敵な作品が多かったです( ◠‿◠ )
やっぱり石版ならではの、独特の風合いってぇものがあるんでしょうねぇ。
ぼくも美術にはとんと馴染みがなくって・・・。
これまたトホホ・・・です。