今日の「天職人」は、名古屋市千種区の「豆屋主人」。(平成十七年八月二十三日毎日新聞掲載)
師走になれば七輪で 鍋がコトコト音立てる 母が煮物を教え込む 嫁入り前の身支度に 今年も豆(忠実/まめ)であればいい 母は御重を前にして 御節の由来あれこれと 俄仕立(にわかじた)ての嫁作り
名古屋市千種区豆のはっとり、二代目主人の服部克己さんを訪ねた。

「豆は子孫を遺す、エネルギーの固まりだでね。でも人間と一緒で、周りの環境の変化に弱いんだわ。だでその年の天候によっては、出来不出来に大きな違いが出る」。 克己さんは、額に汗を浮かべて笑った。
通りに面した店の引き戸は開け放たれ、通り過ぎる車が熱風を運び入れる。
店内には年季の入った木箱が並び、色とりどりの豆が艶を放つ。

豆のはっとりの創業期は、克己さんの父が戦地から復員した昭和二十二(1947)年に溯る。
まだまだ戦後の混乱が続く今池で、父は担(かつ)ぎ屋をしながら家族を支えた。そして翌年、克己さんが二男として誕生。
父は小さな店を構え、豆と種を主に扱う服部種店(旧店名)を開業した。
「とは言え、混乱の時代でしたから、売れるもんなら何でも、油まで売っとったらしいですわ」。
克己さんは高校卒業後、薬品関係の会社で営業職についた。「二年半は勤まったんだけど、やっぱりもともと向いとらんのかなあ。逆に店を継ぐはずだった兄は、私のネクタイ姿を羨んで」。
〝豆を煮るに萁(まめがら)を焚く〟のように、兄弟が傷付けあい争ったわけではないが、互いの得て不得手を認め合い、前向きに互いの人生を入れ替えることになった。
使い勝手のいい大豆に金時。うずら豆にとら豆。鶴の子大豆に白花豆。ぜんざいに最適な大納言、餡子用の小豆(しょうず)。青えんどうにひたし豆と紫花豆(むらさきはなまめ)など。
毎年十月中旬頃になれば、十四種類の新物が店先を飾る。
新物の到着を我先にと求める客。父と二人、升とスリ棒を片手に、量り売りに追われた。
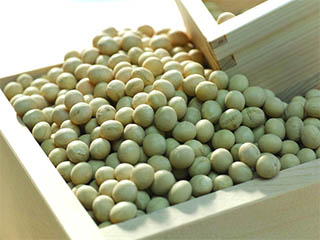
「こうして升に豆を並々と入れ、手前から向うに向かって下げるようにしながら、スリ棒で上っ面の豆を落すんですわ。升を平らにしたままだと、豆の隙間が詰まってしまって、豆が余分に入り込むからって、よう父に叱られました」。
すっかり家業も板に付き、車好きが高じて毎週末になると、夜通しラリーレースに出場。大きなレースを征したほどの戦績も持つ。「私は主にナビゲーター役。毎週東名阪のレースを、転戦して歩いとった。そんなラリー呆けだで、母が亡くなってまったんだわ」。
翌年、近所の知り合いから見合い話が持ち込まれた。
「『前からお母さんに頼まれとったんだわ』って。妻も父と私だけの、男所帯を見るに見かねて、嫁に来る気になってくれたのかも」。三十四歳で妻を得、三人の子宝に恵まれた。
昭和も終焉を控え、日本中が好景気に沸き返り、高級食材も飛ぶように売れた。一部の食通の言葉に踊らされた飽食時代も、バブル経済崩壊と共に沈静化へ。
平成に入ると克己さんは、丹波篠山農協と折衝し、黒豆の販売を開始した。「丹波の黒豆は、味が王様だでね。まあ値段は、北海道産大豆の三倍近いけど」。
毎年十二月五日頃に入荷されると、心待ちにしている客がひっきりなしに訪れる。
沸騰した湯に黒豆を一晩浸け、ふやけて薄皮が破れれば、後はもう煮るだけ。
粘り気のある黒豆は、家々独自の煮汁を蓄え、艶のある柔肌に中に、ほっこりとした独特の食感を忍ばせる。
「今まで一度だけ台風の影響で『篠山の黒豆売切れ』って看板を、暮れも迫ってから出さなかんで、断腸の思いだったわ。篠山じゃない他所の黒豆なら、いっくらでも手に入ったんだけどね。家はいい豆だけを、それなりの値段を守って売らせてもらうのが信条だでな」。
上り框(あがりがまち)に腰掛けた克己さんは、ちょっぴり照れ臭気にそうつぶやき、火の無い夏火鉢に手をかざした。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。


おはようございます。
・豆屋主人のお話ですね。
・色々な豆(大豆,小豆,黒豆,うずら豆)を、仕入ているのですね。
・豆腐屋さん等の方が、買いに来るのかな?
・豆屋専門の店は、行った事ないですね。見た事ないです。
小豆はばあちゃんにお手玉を作ってもらった時に入れて貰いました。よく乾かして入れなきゃ虫がわいちゃうよ。
ばあちゃんのあんこと煮豆は美味しかったな(´∩。• ᵕ •。∩`)
煮物は、年季に勝るものはないみたいですよねぇ。
おはようございます。
・私は、豆料理(豆腐等)好きです。
・個人の方も豆屋さんで、買うのかな?計り売りなら出来ますね。
・良い豆を、販売しているのですね。
以前は、こうした豆と種を商うお店が身近にありましたね。グラム売りでしたね。
おかあちゃんが買ってきた大豆の袋に手を突っ込んで、混ぜ混ぜするのが好きでした。^ – ^
ところで、昭和の頃は、お見合い話をよく持ってきて下さったのですね。
そうですよねぇ。
お見合いは、年頃の証だとか。
残念なことにぼくは、一度もお見合いの経験がありません!
一度はお見合いとやらを、して見たかったものです。
こんにちは 豆の専門店って初めてお目にかかりました 私も52年生きてきて「へ~こんなお店や職人さんの世界があるんだ~!」って見させていただく事がたくさんありますね~ それと「お見あい」・・オカダさんはモテモテで知り合う機会が一杯あったからお見合いとは無縁だったのかも・・・?因みに私は30前半に2回程お見合いした事がありますよ♪ししおどしがカタ~んっていうような立派なところで会うとお思いでしょうが私の時は決まって喫茶店でしたね(笑)結果ですか?結果は残念ながら・・・って
ところでしたかね 若かりし頃の思いででした
でもそこでお見合いが成立しちゃっていたら、奥方様や幹ちゃんに出会うことはなかったんでしょうから、これがよっちゃんを待ち受けていた人生なんだろうねぇ。
良かったじゃない!
結果オーライ!
むか〜し 母親がおはぎや田舎饅頭を作ってくれました。
前の晩から小豆を水につけて…
あんこが出来上がってくる あの優しい匂い。でも大変なんですよね あんこ作りは。
もち米を丸めるのは 私や妹の担当。
さらし布にのせたあんこでもち米を包むのは 母親担当。
いつも こしあんでしたが 一ヶ所もデコボコすることなく サラ〜っときれいな仕上がり。
私も何度か作った事があるけど やっぱり敵いませんね。
そうですかぁ!
漉し餡とはこれまた上品ですねぇ!
家なんて粒餡の牡丹餅専門でしたねぇ。
「天職一芸〜あの日のPoem 154」
お豆さんの種類をご紹介頂きありがとうございます。使い勝手のいい大豆、金時しかなじみがなかったです。母の金時豆美味しかったなぁ〜。ぷちっと白い中身が見えてるのが特に好きでした。
ぼた餅 おはぎと名前の変わるのが子供の頃は不思議でした。
そうなんですよねぇ。
ぼくも牡丹餅とお萩、何処からどう見ても同じなのに、何がどう違うんだろうって、不思議でなりませんでしたもの。
本当の理由を知って、なるほどなぁと、先人の歳時記のとらえ方に感銘を受けたものでした。