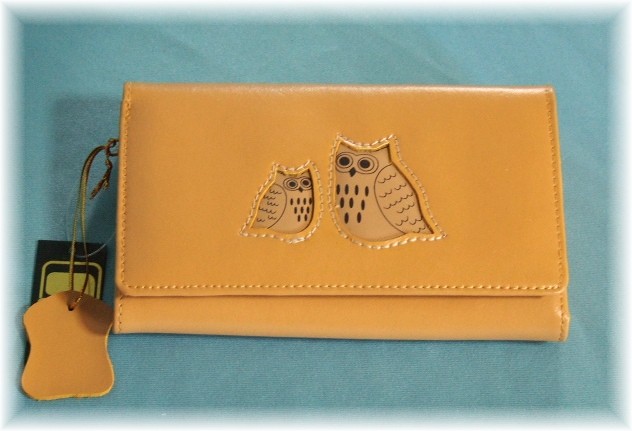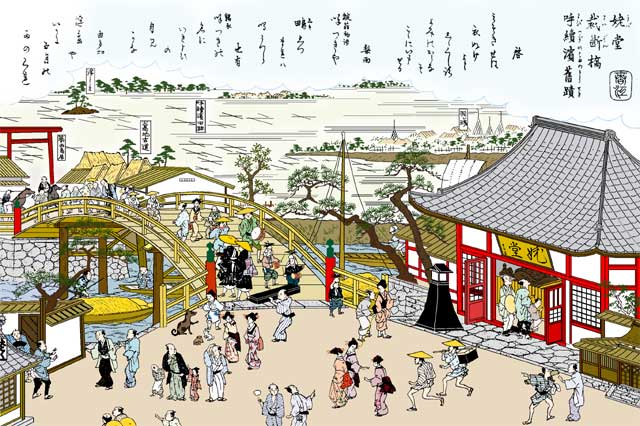「素描漫遊譚」
「三味の撥捌き」
「名古屋名物 美味ゃあもんなら かしわにういろうにきしめんに 味噌カツ天むす海老フリャア」。
色艶やかな着物姿で、陰陽の風情を弾き分ける見事な三味の撥捌き。
 写真は参考
写真は参考
艶っぽさを浮かべた表情に、透き通る高音の美声。
『天は二物を軽軽しくも、与えたもうたというのか!』。
名古屋市千種区の民謡家、N.Kさん(57)のステージを拝見するたび、そう感じてしまう。
出来ることなら月明かりの元、盃を傾けながらほろ酔い気分のまま、しっとりと拝聴したいものだ。
冒頭の一節は、Kさんのライブに欠かせぬ「語り物」。
海の東海道と呼ばれ、熱田の宮の宿から桑名の宿まで、海上七里の道程を結んだ七里の渡し。
宮宿の当時の往来に想いを馳せながら、現代名古屋の風情を織り込んだ「名古屋名物」と呼ばれる語り物。
Kさんが作詞を手掛けた人気作品の一つ。
Kさんは、千種区今池の寿司屋のお嬢様として生まれた。
今でこそ全国から持て囃される「名古屋嬢」の、先駆的な世代の一人であったに違いない。
祖父と父の影響で、幼い頃から三味の音に囲まれながらも、西洋音楽を志しピアノの練習に明け暮れた。
高校3年の時、父親の誘いで民謡の会に連れ出され、三味線との運命的な出逢い。
「ドソドが『どびん』。『やかん』とか、父から口三味線で教わって。もともと音楽好きだったでねぇ」。
そんなある日、三味線を抱え持ち民謡の稽古へと向かった。
交差点で幼馴染とバッタリ。
「あんたあ!何処行くの?そんなん持って」と問われ、Kさんは「さすがに恥かしくて民謡とは言えず、『端唄だて』」と答えたとか。
時代はグループサウンズの全盛時代。
日本の古典的な民謡を、うら若き番茶も出花の18歳の娘にとって、口にするのも憚られた。
短大卒業後は、家事手伝いと民謡のお稽古。
「大人になったら、長唄のお師匠さんになりたいなって」。
そんな矢先、父は名立たる津軽三味線奏者を、家に招いた。
魂を揺さぶるような、津軽三味線の荒く激しい音色が、Kさんの五感を釘付けに。
奏者が名古屋に滞在した1ヶ月間、無我夢中で「六段」の曲を習い奏法を学んだ。
再び某民謡会のお稽古へ。
「撥が違う!叩き方が違う!って師匠に叱られて。『そんな乞食三味線、何処で習って来た!』って、津軽三味線を邪道と考えるような、偏見を持っとったんだろうね。それでその民謡会には、嫌気がさして」。
その後もKさんは、津軽三味線に魅せられ続けた。
世界デザイン博に名古屋が沸いた15年前。
白鳥会場から堀川を下った、宮の渡しの町並みに、Kさんは興味を惹かれて行った。
やがて興味は、庶民の中で息づいた文化へと。
 写真は参考
写真は参考
「それで初めて、都々逸発祥の地が、宮の宿だったと知って。どうやって出来たのか?誰が歌い始めたのか?って興味津々」。
宮の宿、東外れの八丁畷入口。
寛政12年(1800)秋、蜆汁を売る鶏飯屋という安直な茶店が出来、お仲やお亀といった女中が客を持てなしたとか。
その頃、関東から潮来節が流れ着き、お仲やお亀が盛んに替え歌として唄い広めた。
時を同じくして、神戸の町に大きな旅籠が開業し、東海道を行き交う旅人で賑わい、二人の替え歌はやがて神戸節と呼ばれ、囃子言葉から「都々逸」に。
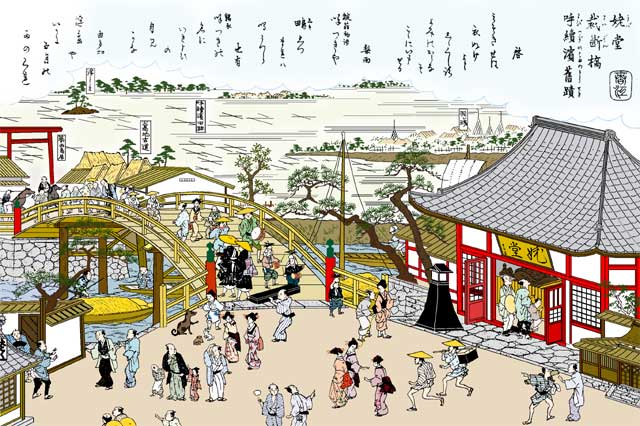 写真は参考
写真は参考
『お亀買う奴 頭で知れる 油付けずの 二つ折れ そいつはどいつだ どどいつ どいどい 浮世はさくさく………』と、Kさんは口ずさんだ。
七里の渡しの常夜灯を背に、往時の伊勢の海原を見つめながら。
 写真は参考
写真は参考
弦を指で棹に押し付け、ゆっくりと左から右へと指を滑らせる「糸音」。
奏者の含みと余韻を、聞こえないほど微かな残響音から聞き取る。
「打指」と呼ばれる奏法は、文字通り弦を指で打つ。撥で爪弾く音とも、微妙に異なる音色だ。いずれも閉ざされた座敷の、静けさ故になせる三味の技。
「人の心かなあ。消え入るように揺れる音が」。
一方の津軽三味線は、荒々しい撥捌きで、まるで厳寒の凍て付く夜を引き裂くように聞こえる。
 写真は参考
写真は参考
「がさつだけど、奥が深くて凍みるんだわ」。
『三味の種類に貴賎などない』。
ぼくには、Kさんの心の声が微かに聞こえた気がする。
このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。